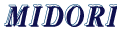
第七官界彷徨 尾崎翠を探して
浜野佐知監督作品

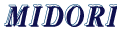 |
第七官界彷徨 尾崎翠を探して浜野佐知監督作品 |
 |
『第七官界彷徨 尾崎翠を探して』映画概要
恋愛に成功するのは、植物の蘚(こけ)だけ。人間はみな、片恋か失恋ばかりしている…こんな奇妙な小説「第七官界彷徨」を書いた尾崎翠は、一時忘れられた幻の作家でした。時は、翠が生まれて一世紀以上経った2004年。彼女の作品と人生をコラージュした、この映画の完成とシンクロするように、新たな再評価が、静かに、深く、インターナショナルに進行中です。カラー作品、108分、35ミリ&16ミリ、モノラル録音。
監督=浜野佐知/脚本=山崎邦紀/
撮影=田中譲二/照明=上妻敏厚/音楽=吉岡しげ美 キャスト=白石加代子/吉行和子/柳愛里/ 原田大二郎/白川和子/宮下順子/横山通代/石川真希
|
●尾崎翠フォーラム・in・鳥取 2002●-02年7月6日&7日/鳥取市・岩美町レポート- |
 |
▲今年は鳥取県民文化会館第一会議室で開かれた。 |
昨年、盛大にスタートした「尾崎翠フォーラム・in・鳥取」。第2回目の今回は、派手なイベントは控え、尾崎翠の作品を味わい、考え、ディスカッションする、実質的なフォーラムとなりました。7月8日は、尾崎翠の命日ですが、それを前に、6日と7日の両日にわたって、全国から愛読者や研究者が集合。中にはアメリカから一時帰国中にこの催しを知り、参加した女性もいるなど、地域や年齢を越えた翠ファンの存在をうかがわせます。 会場は、昨年と同じ鳥取市の鳥取県民文化会館ですが、今年は階段教室風の第一会議室を使用。シンポジウムなどに適した、落ち着いた会場です。午後1時45分に、フォーラム実行委員会監事で、この日の司会を務める角秋勝治さんが開会を告げ、主催者の土井淑平代表が挨拶しました。なかで、フォーラムを前に続けて亡くなった塚本靖代さんと矢川澄子さんを追悼、とりわけ昨年のフォーラムに分科会のパネラーとして参加してくれた塚本靖代さんに触れた時には、思わず涙ぐんだ人たちが、わたし以外にも相当あったはずです。 お祝いの言葉は、昨年に引き続き、片山善博・鳥取県知事と、榎本武利・岩見町長。全国的にも注目されている、ニューウェーブ知事の片山さんですが、挨拶の中で翠の「新秋名果」の一節を諳んじてみせたのにはビックリ。ウラン残土の問題で、住民訴訟をバックアップしたりする知事は、さすが違うなあと心から感心しました。東京の慎太郎都知事などとはまったく違って、落ち着いた知性が光ります。 今年のメインの講演は、歌人の林あまりさんによる「尾崎翠の小宇宙-短歌と少女小説-」。林さんは「グッバイ、センチナウタヨミ-尾崎翠、歌のわかれ-」という、歌人ならではの尾崎翠論を発表していますが、一方、2000年の日本インディペンデント映画祭で『第七官界彷徨・尾崎翠を探して』に「林あまり賞」を与えてくれました。素晴らしい選評に、浜野監督以下、スタッフのみんなが感動したものです。この日は、初期短歌を検討しながら、なぜ翠が短歌に別れを告げることになったのか、また少女小説のジャンルで、もしかしたらライバルであったかもしれない吉屋信子との比較を通して、翠の少女小説がどのように『第七官界彷徨』の世界につながって行ったかなど、柔らかな口調で講演。詳細は、尾崎翠フォーラムのHP、および報告集に発表されますが、わたしは個人的に、翠が日本女子大を自ら退学したことを取り上げて「かっこいいな。決めるところは、バシッと決める」のが翠の流儀、と話されたのが、とても愉快な印象として残っています。 講演の後は、浜野監督と林あまりさんのトーク。登壇しただけで、自他共に、いきなりボルテージが上がるのが、浜野監督のキャラクターですが、ほとんど鳥取が「第二の故郷」化しています。その後、パネル・ディスカッション「尾崎翠の見た夢は…」。詩、和歌・短歌、シナリオ、の3ジャンルから翠の作品とその可能性を検討するというもので、地元の詩人の井上嘉明さん(=当然、詩)、大阪の石原深予さん(大阪大学文学修士=和歌・短歌)、京都の森澤夕子さん(仏教大学大学院=シナリオ)がパネラーです。強力な布陣ですが、コーディネーター兼司会がわたしというのが、いまいちネックだったような気がしてなりません。パネラーの皆さんの大変面白い発表がありましたので、具体的にはやはり尾崎翠フォーラムのHPおよび報告集をご覧ください。 |
|
 |
 |
|
| ▲林あまりさんと浜野佐知監督のトーク。2000年の日本インディペンデント映画祭の「林あまり賞」以来の再会。 | ▲パネルディスカッションのパネラー。左から井上嘉明さん、石原深予さん、森澤夕子さん。 |
なお、昨年に引き続き、今年もまた新資料が発掘され、フォーラムの席上で発表されたことは特筆に価します。これは尾崎翠が、同郷の民俗学者で画家の橋浦泰雄あてに出した3通の書簡で、橋浦に関する研究書をまとめた歴史学・民俗学者の鶴見太郎氏が、遺族から預かった資料の中から確認したものです。この手紙の存在については、鳥取市歴史博物館「やまびこ館」の佐々木孝文・学芸員(フォーラムの運営委員でもあります)が推測、示唆し、それを受けて石原深予さんが鶴見太郎氏に問い合わせて明らかになったものです。現存する翠の手紙では、もっとも古いものだそうですが、これについてはすでに石原深予さんがフォーラムのHPに書いていますので、ぜひ参照してください。 また、今年のフォーラムに時機を合わせ、代表の土井淑平さんの『尾崎翠と花田清輝-ユーモアの精神とパロディの論理-』(北斗出版)という、まことにタイ ムリーな著書が出版されました。これは昨年のフォーラムに向けて『ファイ 人文学集鳥取』の特集号「尾崎翠のコスモロジー」に寄稿された大型評論をベースにしながら、全面的に書き下ろしたものです。近代日本の精神史において稀有の光を放つ、翠と清輝という超個性的な出会い(いや、清輝流に言えば「個性」はすでにない?)に焦点を当て、この二人の作品が何故今わたし達の心を強く惹きつけるのか、現代の視点から読解しています。昨年の評論はいささか難解でしたが、今回の書下ろしでは「笑い」のテーマが快活に展開され、吹き出す場面も少なくありません。地元鳥取で始まった尾崎翠フォーラムの運動の貴重な結実のひとつだと思われます。(本HPの「文学」コーナー参照) |
| 『尾崎翠フォーラム』 http://osaki-midori-forum.com/index.php |
| (02・08・26/ヤマザキ) |

|

|
|
<尾崎翠文学散歩ツアー> 2日目の7月7日は、鳥取駅前に9時に集合し、半日のバスツアーに出発。ガイドは 鳥取県立山陰海岸自然科学館館長でもある運営委員の西尾雄二さん。まずは市内の養源寺で、8日の命日を前にお参り。その後、面影小学校を回って岩美町に向かいました。 網代漁港の翠が下宿した僧堂を見た後、岩井温泉に入り、尾崎翠資料館、西法寺、旧岩井小学校などを訪ねました。その後、浦富海岸の絶景を見たり、透明な海に裸足で入ったりした後、ビジターセンターでお昼を食べ、取りあえず現地解散。多くの人は、そのままバスで鳥取駅に向かいましたが、砂丘や岩美町に残る人もいました。 |
||
 |
||
| ▲鳥取市内の養源寺。翠の墓所の前で。 | ||
 |
||
| ▲生誕した岩井温泉の西法寺で。 | ||
 |
 |
|
| ▲墓所の石碑と案内板は、99年に松本さんたち親族が作った。 | ▲面影小学校の石碑の前で、ガイドの西尾さん。 | |
 |
 |
|
| ▲網代漁港の僧堂の上の道路から、網代の家並みと漁港を望む。港の右奥が鳥取砂丘。 | ▲西法寺。 | |
 |
||
| ▲なぜか気になる西法寺の屋根の彫刻。 | ||
 |
 |
|
| ▲旧岩井小学校。 | ▲岩井温泉のメインストリート。逆側に壮絶な夕日が落ちる。 | |
| <岩美町・番外編> | ||
 |
 |
|
| ▲網代漁港のイカ釣り船のライト。 | ▲映画の撮影で、老人ホームを翠と松下文子が訪ねるシーンを撮った多鯰ヶ池に立つのは、岩美町の川上課長と浜野監督。 | |
 |
 |
|
| ▲美しい多鯰ヶ池に浮かぶ蓮の花。 | ▲網代の、明治からある古いトンネル。僧堂から蒲生川の河口に向かう位置にあり、もしかしたら翠は旧大岩小学校に通うのに、このトンネルを朝夕通ったかも…。 | |

|
● 追 悼 ●-塚本靖代さん、石原郁子さん、矢川澄子さん- |
 |
|
▲00年秋、コロラド大学の学会に参加。右から、塚本靖代さん、浜野監督、堀ひかりさん、溝口彰子さん。大学構内を移動中。 |
街を歩いてたら、不意に「こんな馬鹿なことってあるものか」というフレーズが頭に浮かんだ。なんだったろう? すぐには思い当たらず、もどかしい。ずいぶん経って、吉岡しげ美さん歌う茨木のり子の詩「わたしが一番きれいだったとき」の一節だったことに気づく。立て続けに亡くなった3人の方々に、不躾な連想だったろうか。正確には、「わたしが一番きれいだったとき/わたしの国は戦争で負けた/そんな馬鹿なことってあるものか/ブラウスの腕をまくり卑屈な町をのし歩いた」 本当に「そんな馬鹿なこと」が起こったのだ。2002年の5月27日に石原郁子さん、29日に矢川澄子さん、そして6月14日に塚本靖代さんが亡くなった。いずれも、わたし達の映画に当初から同行してくれた方たちだ。茫然とする渦中で、わたしのパソコンがパンクし、その修復に血眼になりながら、わたしはほとんど気が変になりそうだった。なかでも、塚本さんの享年が29才であったことを知り、胸を衝かれた。下手すると親子ほども年の違う彼女を、わたしはどれほど頼りにしていたことだろう。わたしは迂闊にも彼女の年齢を意識に上せたことがなかったが、29歳の無念を思うと未だに遣り切れない。 | ||
* |

|
|
わたし達の映画『第七官界彷徨・尾崎翠を探して』は、発端から論争や対立をはらんでいた。なかでも熾烈を極めたのは、尾崎翠の発掘者とされ、二度の全集(1979年、創樹社。1998年、筑摩書房)の編者である稲垣眞美氏と、彼を権威とする一派との暗闘だった。もとより脚本担当のわたしは、氏のオッサン的解釈に疑問を持ち、加藤幸子さんや矢川澄子さんの新鮮な読解に依拠したが、尾崎翠を私物化する氏にとって、自分が介在しないところで映画が作られるなど不届き千万だったらしい。妨害は陰湿、執拗だったが、わたしはどうしてこんな事態が起こるのか、氏の翠に関する評伝はもちろん、酒やワインに関する著書や、酒造業界との繋がりまで洗い出し、批判的に検討した。そこに現れたのは、かつて志を持ち、悪くない仕事もしながら、歳月とともに権勢欲や、その他世俗の欲に身をゆだね、かつ無自覚になっている「文化人」の堕落形態だった。 | |||||
| 矢川さん、塚本さん、石原さんに出会ったのは、そうした暗闘の渦中だった。矢川さんの著書『野溝七生子という人-散けし団欒-』(1990年。晶文社)という美しい書物の次の一節は、脚本のスタートラインから、わたしの頭の中で鳴り響いていた。渡辺えり子さんの『第七官界彷徨』を原作とした舞台「オールド・リフレイン」を見た後の感想である。「尾崎翠といえば、なァちゃん、おなじ頃に『女人芸術』でデビューしたのでご存じだとおっしゃってましたっけ。なァちゃんよりは一つ年長のその尾崎さんの、半世紀も前に書かれた『第七官界彷徨』の世界が、こうしてすぐれた後進の手によって現代の舞台の上にみごとに甦えるのを見て、わたしもあらためて思ったのです。野溝七生子の作品もこんなしあわせな目にあわせてあげられないのかな、と。尾崎さんもなァチャンも、資質こそちがえ、世が世ならば少女漫画家として大いに名をなしていたかもしれない、などといったら、明治生まれのあなた方はどんな顔をなさるでしょうか」 |
|
||||
そうだ、少女漫画家の尾崎翠を想像してみよう。矢川さんの最後のフレーズは、わたしにどれほどの推進力を与えてくれたか知れない。浜野監督と相談し、矢川さんと加藤幸子さんにインタビューの形で特別出演してもらうことになった。そして大手町の国際フォーラムの喫茶店で、矢川さんとお会いした。地球の引力を離れ、軽々と浮遊するような、小柄なこの人は、「わたしに何をさせようっていうのよ」と涼しく笑った。稲垣氏が脚本にイチャモンを付けてきた時、わたしは一度だけ浜野監督とともに氏に面会したが、女性には詩心がない、などと言いつつ、矢川さんが出演するようなら、自分、すなわち氏が翠の臨終に間に合ったというフィクションがあってもいいではないか、などと示唆して、わたしは心からバカヤローだと呆れ果てた。氏が30年ほど前、鳥取を訪れたのは、翠の死後、『アップルパイの午後』(1971年。薔薇十字社)が出版された後であり、それが残念でたまらないのだろうが、こんなクソオヤジに出番はない。 わたし達は、稲垣氏が作り上げた伝説、死を前に翠が「このまま死ぬのなら、むごいものだねえ」と呟きながら大粒の涙を流した、という例の見てきたようなエピソ-ドに、翠の人生や作品を重ね合わせ、シンボライズしようとする見方を、根底から覆すのを試みたのだ。映画の冒頭で、死の床の翠が「このまま死ぬのかねえ」と言って、受容するかのように静かに微笑するのは、わたし達の姿勢をド頭から明らかにするためであった。 | ||||
* | ||||
多くの人たちのカンパや、文化庁、東京女性財団の助成によって、なんとか制作にこぎつけた98年春、青山の東京ウィメンズプラザで、白石加代子さんや柳愛里さんが出席し、制作発表を行った。多くのマスコミに働きかけ、多くは無視されたが、わたしは、『菫色の映画祭―ザ・トランス・セクシュアル・ムーヴィーズ―』(1996年。フィルムアート社)の著者に来てもらいたいと念じた。出版社に掛け合って、半ば強引に石原郁子さんの電話を聞き出し、ファックスを送った。わたしにとって、尾崎翠と松下文子の友情こそ一方のメインテーマであり、評価の定着しないレズ&ゲイフィルムの領野に分け入って、個々の作品を愛しげに論じた、この著者に、ぜひ来てもらいたいと思ったのだ。残念ながらスケジュールが合わず、石原さんは来れなかったが、未知の人間からの直前のファックスに対し、人懐こい手書きのファックスを返してくれた。 |
|
|||

|
|
わたしが初めて現実に石原さんとお会いしたのは、最後に撮影されたクィア・パーティーの時だった。めげずに再度お誘いしたら(エキストラに!)、丸いサングラスにチャイナドレス風の、チャイニーズマフィアみたいな扮装で現れ、すっかりわたしは嬉しくなってしまった。ただ、あのパーティーシーンのどこに石原さんが映っているか、何十回となく観ているはずのわたしも確認できていない。奇妙な集団のどこかに居られるはずなのだがー。石原さんが翠の愛読者でもあったことを知ったのは、ずいぶん後のことである。 一方、青山の制作発表に、忽然と現れたのが、東大の大学院の博士課程に、学習院から移ったばかりの塚本靖代さんだった。たしか、後に『週刊金曜日』で二度にわたり、映画と浜野監督を批評してくれた川口恵子さんの紹介だったと思う。その場で、尾崎翠をテーマにしたという修士論文を送っていただくようお願いしたのだが、後日送られてきた「尾崎翠論―『第七官界彷徨』を中心とした戦略としての『妹』について」(1997年)を読みながら、わたしは快哉を叫んだ。それまでわたしは公刊された尾崎翠論しか読んでいなかったが、研究の世界ではこうしたフェミニズム感覚あふれる論文が書かれていたのだ。これこそわたし達が待望した尾崎翠論だ! 愉快のあまり、ところどころ吹き出しながら読了したことを、塚本さんに手紙で知らせたら、この修士論文はフェミニズム批評に無理解な教授のもとで、苦闘しながら書いた、笑いながら読まれる日が来るとは思わなかった、と返信で喜んでくれた。最近になって、教授のみならず、研究の同僚も含めて、塚本さんにとって酷い環境であったらしいことを知ったが、彼女もわたし達も、異なった業界で孤立し、悪戦苦闘していたらしい。 翠の遺族に恩義を売る稲垣氏の妨害は執拗だったが、わたしは映画のパンフレット(1998年)に、修士論文をコンパクトにまとめた「第七官界彷徨」論を依頼し、尾崎翠論の新しい地平を示すと同時に、わたしはわたしで稲垣氏の実名をあげ、論難する文章を書いた。映画関係者には、難しい文学論や、「権威」を罵倒する文章など載せて、映画パンフの体をなしていないと、きわめて不評だったが、わたしなりに覚悟を決め、これに起因するトラブルは個人的に責任を負うつもりでやった。ただ、もし稲垣氏を「権威」とするなら、それに楯突くマイナーな一党、それもピンク映画上がり(上がってない?)の下品な連中と、塚本さんが一緒くたにされる恐れがあったが、それを言っても彼女は意に介さなかった。含羞をたたえた優しい話し振りとは裏腹に、梃子でも動かせない強さが彼女にはあった。映画のわたし達と文学研究の塚本さんとの間に一線を画すべく、わたしは注力したつもりだったが、後に塚本さん自身が稲垣氏に異議を申し立てることになった。 雑誌『鳩よ!』が99年11月号で尾崎翠の特集をした際、例によって稲垣氏が与太話を書き、「私のピーターパン」の作者、岡愛子=尾崎翠説を唱えた。しかし、二人が明確に別人であることを知る塚本さんは、とんだデマが一部にでも定着することを心配し、その旨編集部に申し入れた。こういう時の塚本さんに、躊躇いはなかった。翌年4月号の目立たない場所に、ひっそりと稲垣氏の釈明が掲載されたが、敵対する映画のパンフの執筆者でもあることを知ってか知らずか、「横浜市の塚本靖代さんという、尾崎翠の研究も進めておられる方から」指摘があったことを記している。 この『鳩よ!』の特集号の巻頭には、稲垣氏の提供と解説による「未発表作品『エルゼ嬢』」の写真版を麗々しく掲げていたが、これまた尾崎翠の創作ではなく、シュニッツラーの小説の冒頭部分の翻訳草稿であったことが判明したと、稲垣氏の小文の後に、編集部からの小さな訂正が載った。これも塚本さんが編集部に伝えたことだが、雑誌が出た直後からインターネットで指摘されていたという。しかし、この「松下文子」の署名がある草稿も含め、筑摩書房から定本全集2巻が出た際に喧伝された新資料、松下文子宅に「秘蔵」されてあった「朱塗りの文箱」から出てきた未発表原稿については、「瑠璃玉の耳輪」も含め、果たしてすべてが翠自身のものか重大な疑義がある。これについては、これから書く予定の編集後記を参照していただきたい。 | ||
* |

|
| 矢川さんと加藤幸子さんのインタビュー撮影の時に、塚本さんを誘ったら喜んで来てくれた。尾崎翠についての評論では、加藤さんの『尾崎翠の感覚世界』(1990年。創樹社)はエポックメイキングなものだし、矢川さんは文庫版「ちくま日本文学全集」(1991年。筑摩書房)の尾崎翠の巻の解説を書いた。しかし、それだけでなく、塚本さんの博士論文の対象は、尾崎翠、吉屋信子、そして野溝七生子の3人だったのだ。その直後に開かれた矢川さんの出版記念会(『矢川澄子集成』1998年、書肆山田)に、塚本さんとわたしが参加し、塚本さんは矢川さんに野溝七生子の縁者を紹介されたと言って、とても喜んでいた。わたしも嬉しかった。マイナーな映画に関わっていただいたことが、少しでも彼女の研究のプラスになることを願っていた。(筑摩の文庫の解説は、『「父の娘」たち―森茉莉とアナイス・ニン―』1997年、新潮社、所収) |
|
| しかし、矢川さんのインタビュー撮影に関して、わたしは未だに消せない悔いが残っている。さて撮影という段になり、カメラマンが、椅子に座った矢川さんの表情が影になるといって、かぶっていた帽子を脱ぐことをお願いした。矢川さんは、言われるままに脱いでくれたのだが、明瞭には意識できないくらいの小さな石が、わたしの胸に落ちた。その時は迂闊にも傍観してしまったのだが、矢川さんは撮影用に帽子を準備してきたのであり、その後いくつかの矢川さんの写真を見るにつけ、実に似合った帽子をかぶっている。あれは矢川さんにとって大切なアイテムではなかったか? わたしが撮影部や照明部を説得してでも、帽子をかぶったまま登場していただくべきではなかったか? 後に岩波ホールで試写を行った際、矢川さんの知人の女性作家が、矢川さんは妖精のような方なのに、普通の人のように映っている、と語られ、わたしの胸は塞いだ。今年の7月末に、早稲田で行われた「送る会」の壇上には、大きな帽子をかぶった矢川さんの、大きな写真が掲げられていた。 | ||
* | ||
石原郁子さんが、最後のクィア・パーティーのエキストラに来てくれることになった前後、わたしは本屋で彼女の小説集に出会った。『月神祭』(1997年。光風社出版)というその本は、「JUNE小説」「やおい小説」と呼ばれる、男同士の愛を描いた耽美小説で、すでに映画評論家として一家を成していた石原さんは、一方でアウトサイダーの小説家でもあった。わたしはその中の「監督」という短編の、ひとつのシーンで思わず涙ぐんでしまったが、それを石原さんに告げると、可笑しそうに笑っていた。わたしは、日本の商業映画でもっともマイナーなジャンルである「薔薇族映画」(ピンク・ゲイ映画の業界用語)の監督でもあり、その年の暮れの自作の試写に、石原さんと塚本さんをお誘いした。塚本さんは期待したような「薔薇族」の映画でなく、むくつけき男の裸体のオンパレードに大いに失望したらしかった。しかし、その日初めて会った石原さんが、彼女の知的好奇心に充分応えられる人であることは言うまでもなく、二人は次の試写に連れ立って行った。見送るわたしは、いくらか寂しかったが、これを機会に交流を深めた二人が、後に同じ病と闘う身になるとは、とても信じられないことだった。 石原さんは、その頃『第七官界彷徨・尾崎翠を探して』の映画評を、『キネマ旬報』の「試写室」(1998年12月上旬号)に書いてくれたが、普段映画雑誌を読まないわたしは、翌年、上映会で知り合った人にコピーをもらって読んだ。尾崎翠の世界も、映画の世界も深く理解した上で書かれた、美しい批評だったが、末尾でわたしの脚本について触れた部分は、明らかに過褒,すなわち誉め過ぎであり、わたしは照れてズボンのポケットにでも突っ込んだような記憶がある。後に、石原さんとのメールのやり取りの中で、この批評を再読する必要が生じたが、しかし貰ったコピーは多分見つからないだろうと、半ば諦めながら探したら、書棚の奥に大切そうにしまってあった。過褒は承知しながらも、自分のシナリオを生まれて初めて誉められて、わたしは嬉しかったに違いない。これ以降も、石原さんはわたしにとって、一貫して過褒の人だった。(この映画評は『イースト・アジアの映画の、美』(2000年、芳賀書店)所収)。 | ||
* |

|
|
98年の夏に、岩波ホールで1週間ロードショー公開されることになり、岩波の方々と協力しながら宣伝活動をした。この時、知人のツテで『週刊読書人』に記事を掲載してもらえることになり、執筆者について尋ねられたわたしは、目黒の読書会が浜野監督を招いてくれた時に知り合ったばかりの近藤裕子さん(現・札幌大学助教授)と、塚本さんを推薦した。近藤さんは映画について、塚本さんは翠研究の現状について書き(『週刊読書人』1999年6月25日号)、どちらも素晴らしい文章だった。わたし達のようなアカデミズムとは無縁の、ほとんど夜盗のごとき(?)グループに、塚本さんのような真摯な研究者が同行してくれることを、どれほどわたしは心強く思ったことだろう。どんな難問がやってきたって、ヘイチャラだ。こっちには塚本さんがいる。こんな具合に、わたしははるか年下の塚本さんを頼りにしていた。 塚本さんは折に触れて、翠に関する論文や資料のコピーを送ってくれたが、当初から翠関係の資料が図書館の奥深くに眠っている(あるいは稲垣氏などによって私蔵されている)実情を憂え、誰もが自由にアクセスできることを望んでいた。わたし達のHPが、遅まきながら00年にスタートした時、塚本さんは尾崎翠の詳細な参考文献目録を提供してくれた。これは、専修大学の畑研究室が1年かけて調査した結果を、HP用に再編集したものだが、この調査に塚本さんも資料を提供するなど協力していたので、畑研究室も快く了解してくれたのだ。人のために労をとることを、まったく厭わない人だった。(畑研究室の研究成果は『尾崎翠作品の諸相』2000年) しかし、この年、しばらく連絡の途絶えていた石原さんが、前年の99年に乳ガンの手術を受けていたことが分かった。メールで治療中の知らせを受けたわたしは、深夜酔って帰ってきて、そのメールを読みながら声を上げて泣いた。翌年、塚本さんのメールでまったく同じことを経験するが、この時もわたしは深夜酔っていた。塚本さんの場合は、00年の秋に米のコロラド大学で開かれた、日本の女性映画作家に関する学会に、親しい友人たちと参加した後のことだった。彼女の学習院時代からの親友で、フィルムセンターの研究員でもあった堀ひかりさん、アメリカに留学中の溝口彰子さん(日本にいた頃は、レズ&ゲイ映画祭で字幕監修したり、来日した監督の通訳をするなど、わたしにはスターのような人だったが、今では帰国し、博士論文に取り組んでいる)、それに浜野監督やわたしなどが参加した。 塚本さんは、尾崎翠の作品と映画について、英語で発表したが、発音に不安を感じると言って、プロジェクターでスクリーンに英文を投射した。しかし、質疑応答になって難しい質問が出ると、腕を捲り上げて答え、一見か細げな声の背後に控えている、はったりや見せ掛けのない、ナチュラルな強気を見たように思った。 後で聞くところによると、コロラドに発つ前に腫瘍が見つかり、しかし良性のものであるから心配ないという医師の診断で、学会に参加したのだという。ところが、帰国して再度診察を受けると、今度は悪性になっていて、この辺り医師の診断に大いに疑問が残る。飛行機の関係で、一人で渡米した塚本さんは、デンバーの空港から、大学のあるボールダーまでのバスの乗り継ぎでひどく消耗したというが、最初から正確な診断が出ていたら、この渡米は見合わせたに違いない。治療に入ってからは、すでに闘病中の石原さんとも情報交換していたらしいが、堀ひかりさんによると、インターネットで北米のガン治療の情報を集め、新しい治療法を探索したり、ガン患者だけのメーリングリストに参加するなど、とても積極的に取り組んでいたという。 01年には浜野監督の新作『百合祭』が完成し、このパンフレットに、わたしは短い感想をお願いした。治療の合間を縫って試写を見に来てくれた塚本さんは、あるシーンを源氏の「雨夜の品定め」になぞらえたり、国文とフェミニズム批評の研究者らしい、面白い着眼のエッセイを書いてくれた。このおばあさん達ばかりが活躍する映画の感想の末尾に、彼女は次のように書きつけた。「願わくば、長生きをして、こんなカッコイイおばあさんになりたい!」。これを読んだわたしは、塚本さんが「長生き」をすでに深く断念しているような気配を感じ、狼狽えた。しかし、まさか、こんなにも早いとは。 | ||
* |

|
|
01年の8月末には『百合祭』の1週間にわたる自主ロードショーを、青山の東京ウィメンズプラザで行ったが、この時わたし達は石原郁子さんの「日本の女性監督の現在とその特殊性」という論文をコピーし、お客さんに配った。これは00年の12月にフランスのパリ日本文化会館で開かれた、日仏女性研究学会主催のシンポジウムの「映画の夕べ」で、『第七官界彷徨・尾崎翠を探して』が上映され、この時パリの観客のために寄稿されたものだ。初めて浜野監督を、日本映画の文脈のなかに位置づけた文献だと思われるが、このパリでの上映自体、石原さんが主催の日仏女性研究学会の皆さんに推薦してくれたものだった。闘病の一方で、批評を書き、著書を上梓し、さらにはわたし達に、こんな大きなプレゼントもしてくれたのだ。(論文は本HPの資料コーナーに収録)。 | |||||
|
この青山での上映には、石原さんも見えて、出来上がったばかりの清々しい映画評論集『女性映画監督の恋』(2001年。芳賀書店)を持参してくれた。この本を脱稿する前に、『百合祭』を観ておくべきだった、書くことはいっぱいあったのに、と残念がってくれた。その後、メールで大変有り難い感想をいただいたが、これについては旦々舎のHPの掲示板を参照してください。<アドレスは「リンクコーナー」>。なお、この「女性映画監督の恋」という言葉は、もともと小説のタイトルとして準備していたものを、今回使ったのだと話されていた。何気ない会話だったが、小説には間に合わない、というような含意があったのだろうか。 この自主ロードショーでは、『第七官界彷徨・尾崎翠を探して』も1日1回上映したが、塚本さんが来られた際には舞台挨拶をお願いし、尾崎翠について語っていただいた。これに先立つ6月初めには、鳥取で第一回の「尾崎翠フォーラム・in・鳥取」が開かれ、塚本さんはこの画期的なイベントのフェミニズム分科会に、パネラーとして参加している。塚本さんも石原さんも、確かに闘病中だったが、一方で立派なお仕事や研究を持続していて、わたしは漠然と、いつか治る、あるいはこのままの状態が続く、と思い込んでいた。 |
|
||||
今年の4月に、浜野監督とわたしは『百合祭』で香港国際映画祭に参加したが、1月の終わりごろに石原さんから「こんなの書いたので」というメールをいただいた。これが香港映画祭のプログラムのための「女性の視点によるピンク映画・ロマンポルノ論」で、大物の浜野監督が登場しているのはもちろんだが、わたしのような評価の対象外の監督にまで言及され、数年前に塚本さんと一緒に見ていただいた「薔薇族映画」にも触れていた。実際に香港に行き、オフィスで若い女性スタッフ達に向かって自己紹介する時、わたしは貰ったパンフレットの中から英訳された石原さんの論文を見つけて、中に記されているアルファベットの自分の名前を指差した。いささか得意げであったろうと思う。石原さんはわたしにとって、最後まで過褒の人であった。 | |||||
* | |||||
塚本さんが、亡くなる一ヶ月ほど前の5月初旬、矢川さんを長野の黒姫山に訪ね、インタビューしていたことを後で知った。堀ひかりさんによれば、塚本さんは今年転移が発見された後も、野溝七生子の生原稿を写真に撮って整理しながら、「できるところまでしておけば、次の人の役に立つから」と語ったという。最後まで研究に向かい合っていた塚本さんだが、彼女よりも早く、なんということだろう、矢川さんが自死された。石原さんの逝去は知らされたが、矢川さんの場合は報道が遅れ、塚本さんは知らずに亡くなったという。 わたしは何度でも繰り返し言い続ける。こんな馬鹿なことってあるものか。この人たちの不在に、わたしはいつまでも馴染まない。 | |||||
| (2002・09・11 ヤマザキ) | |||||
 |
 |
|
| ▲00年、コロラド大学の学会で質疑応答する塚本靖代さん。右は、フェイ・クリーマン助教授と浜野監督。 | ▲01年、東京ウィメンズプラザの上映会で尾崎翠について語る塚本靖代さん。 |
|
※矢川さんや石原さんと違って、まだ研究の成果が本にまとまっていなかった塚本さんだが、あまりにも早すぎた死を惜しむ関係者の手によって、遺稿集が計画されている。あらためて、塚本さんに頂いていた抜き刷り(東大の紀要に発表した「ホモソーシャル体制のなかの『妹』-『それから』を例として」1999年『言語情報科学研究』第4号)や、学会誌に出すべく準備していた「尾崎翠『アップルパイの午後』-妹たちの抵抗」を読むと、素人のわたしではあるが、日本文学のある時代の分析に欠かせない、とても重要な視点を提出しているように感じられる。それはおそらく文学だけの問題でなく、今日の社会のベーシックな部分でもあるだろう。塚本さんは、ジェンダー化された社会につながる、家族の内側の権力関係を探求した。野溝七生子の調査研究も含め、塚本さんの論考がまとめられる日を待ちたい。
|

|
-HPも立ち上げる- |
|
昨年に引き続き、「尾崎翠フォーラム・in・鳥取 2002」が、7月6~7日に開催されます。 6日(土)が、歌人の林あまりさんの講演「尾崎翠の小宇宙-短歌と少女小説-」をメインに、浜野佐知監督と林あまりさんの対談、それに若手女性研究者を中心にしたパネルディスカッション「尾崎翠の見た夢は…」という構成です。その後、交流パーティが行われます。 7日(日)は、尾崎翠文学散歩ツアーで、鳥取駅前からバスに乗り、鳥取市内や岩美町の翠の足跡を残す場所を訪問します。翠の眠る養源寺も訪れますが、思えば、翌7月8日は、尾崎翠の命日でした。(1971年没) 詳しくは、新しく開設され、今後引き続き尾崎翠について鳥取から発信していくホームページ「尾崎翠フォーラム」にアクセスしてください。 なお、林あまりさんの尾崎翠論としては、岩波書店の「短歌と日本人」第5巻『短歌の私、日本の私』(99年5月刊)に所収の「グッバイ、センチナウタヨミ-尾崎翠、歌のわかれ-」が、わたしには鮮やかな印象を残しています。ほとんど筆を置く最後の時期に書かれたエッセイ「もくれん」(1934年)を取り上げ、なかで翠が学生時代の旧作として回想している短歌が、実際にはそのままの形では存在しない「謎」に着目し、翠と短歌の関わりについて論じています。 歌人が、自分の心を、かつて歌人であった尾崎翠の心に重ね合わせる時に生じる、スリリングな出会いと、そこから聞こえてくる「ハロオ、グッバイ」の声。今回の講演では、さらに少女小説にも言及されるということなので、わたしは大好きな少女マンガに通じるような、ピュアな尾崎翠論を夢見てしまいます。 |
||
| (2002・4・10 ヤマザキ) |

|
|
『第七官界彷徨 尾崎翠を探して』上映委員会 |