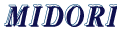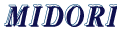●専修大学大学院、畑研究室が『尾崎翠の諸相』発行●
町子の赤いちぢれ毛の行方? 削除された「模倣の偉きい力」とは?
町子は何故「女の子」と呼ばれる?
『こほろぎ嬢』の語り手は、どうして「私たち」という複数なのか?
生新な尾崎翠アプローチの数々に注目
|
尾崎翠の作品を読むのは、もちろん楽しい。尾崎翠の作品についてディスカッションするのも、また別の楽しさです。専修大学大学院文学研究科の畑ゼミ(畑有三教授)が、1999年度の演習で研究した成果を『尾崎翠作品の諸相』としてまとめました。
筑摩書房の『定本 尾崎翠全集』上下巻の発行に刺激されたということですが、これまで発表されてきた数多くの尾崎翠論をベースにして、今日的な視点から、生新な作品論を展開しています。また、1年かけて精査された文献目録も貴重なものです。収録されている論文は8本ですが、例えば、 |
*『初恋』における男の長襦袢(女装)や妹の男装には、どんな民俗学的な意味があるのか、
*『香りから呼ぶ幻覚』の嗅覚と触覚の描かれ方、
*町子の「赤いちぢれ毛」が、作中でどんな運命をたどり、いかなる影響を町子に与えたか、
*町子がいつも「けむったい思ひ」をさせられている名前が、町子にもたらした「分裂心理」、
*町子は「人間の第七官にひびくやうな詩」に到達できたのか、
*削除された冒頭の一行の「模倣」のモチーフがはらんでいる「偉きい力」とは、
*『こほろぎ嬢』のエロスを回避した恋愛は、他作品にも共有されている、
|
|
|
 |
|
等々、まさに21世紀を目前にした現在地点からの興味、関心、問題意識によって論じられています。
どうですか、読みたくなったでしょ? ここではヤマザキが個人的にもっとも啓発された末國善己さんの「異端・図書館・分身-尾崎翠『こほろぎ嬢』試論」を、ピン・ポイントで紹介します。
*幸田当八氏は、なぜ旅から旅を続けながら、研究を重ねなければならなかったのか? それは、氏が研究する「分裂心理学」が、フロイトの精神分析の大きな影響下にあり、この作品が書かれた1932年当時のフロイト説は、帝大を頂点とするアカデミズムの精神医療からすると「異端」の学説だった。怪しげな薬を常用する「こほろぎ嬢」も、二重人格の「ふぃおな・まくろうど」=「ゐりあむ・しゃーぷ」も明らかに異端の人種であり、当時の常識ある人々からすれば、境界の向こう側の奇天烈な世界だったろう。
*「こほろぎ嬢」の経済生活は、いかなる苦境にあったか? ラストで「産婆学の暗記者」に向かって「こんな考へにだって、やはり、パンは要るんです」と声なき呟きを洩らしますが、部屋代や薬代以外に「嬢」は図書館の入館料も支払っていた! 当時は公共図書館も有料制で、1908年開館の日比谷図書館は「特別閲覧料は四銭(回数券の場合十五枚綴りが十八銭)普通閲覧券は二銭(十五枚綴りが十八銭)」で、館外貸出となると、有効期間によって4円(1年)2円(5ヵ月)1円(2ヵ月)という高さです。それから20年も経ってれば「嬢」が払った閲覧料はもっと上がっていたろうし、図書館へ行く往復の電車賃もかかる。末國さんが「こほろぎ嬢」は「悲壮とも思える覚悟で、図書館に通い続ける」と書いているのには吹き出してしまいましたが、経済の逼迫を考えると納得できます。
*「嬢」は図書館の先客を、どうして「産婆学の暗記者」と信じ込んだのか? 1927年発行の『職業婦人調査(看護婦・産婆)』(中央職業紹介事務局)によれば、産婆の月収は2百円~5百円で、事務員やタイピストでは自分一人の生活費にも足りないのが普通だが「産婆にあってはその収入でよく一家の生計を立ててゐるものである」とか。当時の女性が自立するための数少ない職業が産婆であり(そういえば、ヤマザキの祖母が横浜で産婆していたらしい)「産婆学の暗記者」である「未亡人」は、一人で生きていく道を探っていたのではないか。その意味では、自分の世界を守ろうとする「こほろぎ嬢」とも、どこか似通った境遇にあり「産婆学の受験者」は「パンの世界を生きるもう一人の」「こほろぎ嬢」ではないか、と末國さんは指摘します。つまり「ふぃおな・まくろうど/ゐりあむ・しゃーぷ」の分身性が「こほろぎ嬢/産婆学の暗記者」にも通有しているというわけで、これにはわたしも思わず膝を叩きました。
なかで森澤夕子さんの論文「尾崎翠の両性具有への憧れ-ウィリアム・シャープからの影響を中心に-」が引用されていますが「こほろぎ嬢」と対極的な存在として「子供を産むのを助けるための産婆学を勉強している未亡人」という、森澤さんの見方にもわたしは心惹かれるものがあり、批評もまた大いに「分裂」することで豊かになっていくことでしょう。
それにしても、産婆さんの月収や、図書館の閲覧料といった形而下のデータを駆使しながら、大胆な推理を展開する末國探偵の鮮やかな手並みには、すっかり感服しました。
|
●『尾崎翠作品の諸相』目次
「尾崎翠文学の位相」畑有三
「尾崎翠『初恋』に関する一考察」上山和宏
「『香りから呼ぶ幻覚』一「感覚」と深層心理について」チョン スウォン
「尾崎翠『第七官界彷徨』論一小野町子と「赤いちぢれ毛」について
“女くらゐ頭髪に未練をかけるものはないね。”」押山美知子
「尾崎翠『第七官界彷徨』論一《名前》からのアプローチ」南雄太
「尾崎翠『第七官界彷徨』一<詩的>散文という位置」遠藤郁子
「名前を求めて「彷徨」する「女の子」一『第七官界彷徨』試論」横井司
「閉ざされた世界一『こほろぎ嬢』を中心に」高橋由香
「異端・図書館・分身一尾崎翠『こほろぎ嬢』試論」末國善己
「尾崎翠書誌」横井司・編
「尾崎翠参考文献目録」末國善己・編
「尾崎翠映像・舞台化作品目録」末國善己・編
|
■お問い合わせ先■
〒214-8580 川崎市多摩区三田 2-1-1 専修大学大学院 文学研究科 畑研究室
(購入を希望する場合は、頒価1千円+送料)
|
|
★なお、本HPに今回から掲載する「尾崎翠参考文献目録」は、畑研究室が調査したデータの提供を受け、塚本靖代さん(東京大学大学院・総合文化研究科博士課程)が、HP用に再編集してくれたものです。畑 有三先生、畑研究室の皆様、末國善己さん、塚本靖代さん、鳥取県立図書館郷土資料室に心からお礼申し上げます。 |
| (2000.9.23)
|