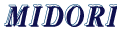
資料コーナー

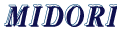 |
資料コーナー |
 |
●日本の女性監督の現在とその特殊性●日仏女性研究学会による |
|
(1)現在の状況 日本では、1985年、東京国際映画祭発足と同時に協賛企画として「カネボウ女性映画週間」が始められ、それが日本で「女性も映画をつくり得る」ことが、「例外」でなく「当然」のことと意識された最初といえる。それ以来現在までの、日本で作られた女性監督による長篇劇映画(映画館で一般公開されたもの)は、別表のとおり(なお、日本初の女性監督作品は1936年坂根田津子の『初恋』)。一覧して明らかなように、監督登録者の半数が女性であるといわれるフランスに比べてはもちろんのこと、他の国々と比べても、日本における女性監督の数は(国会議員、大臣、県知事、会社社長などの数と同じように)まだ極端に少ない。また、著しい特徴として、その数少ない女性監督が、現代の日本の女性の姿を主題とした作品を作ることは、さらに少ない。 (2)理由と歴史 それには日本固有の歴史的な理由がある。 a.初期の日本映画は、当時日本で下層の卑しい仕事とされていた大衆芸能の範疇に入れられ、それは女性の人前での演技を原則として禁じていたため、完全に男性だけの世界だった。また、興行や製作もやくざ者の支配下にあったため、女性は近づけなかった。 b.映画が産業として巨大な利益を生むことがわかると今度は近代的な映画会社が監督を養成するようになったが、監督候補生(助監督として採用)は大学卒男子に限られた。近代的産業となっても、映画の現場はまだ荒っぽい腕力を必要とする根強い男性絶対主義社会であり、それを統治するには、大卒男子でなければならなかった。 c.さらに、TVの出現で映画の人気が落ちると、今度は日本映画は、暴力やセックスシーンなど、《一般家庭の居間では見ることができない》ものを売り物にした。そのため、経済力がなく娯楽を求めて出歩く自由もあまりない女性たちはTV、やや経済力があり知的なものを求める女性たちは日本映画を見限って洋画、男性たちは日本映画という、現在まで続く傾向がこの頃できあがった。 d.また、日本では《女性が若く、可愛らしく、男性に脅威を与えない》ことが伝統的に求められてきた。そのため、映画の主題としても、社会で活動する女性ではなく、常に不自然なほど若く可愛らしい女性がヒロインに選ばれる。また、《知性や教養や技術を持ち、男性スタッフに対して判断を下す、大人の女性》としての女性監督は、この伝統に従って当然敬遠される。 |
|||
| e.女性映画批評家や女性映画製作者も、上記の理由できわめて数が少ない。それも、女性映画監督が自然に出てきにくい社会の状態を作っている。男性批評家たちは《女性の視点に立った作品》を、「女はやはり自分の周囲の狭い世界しかわかっていないから、だめ」と評しがちである。また、映画にお金を出す銀行や製作会社のトップもほぼ全員が男性であるため、まれに女性監督を抜擢しても、彼らが求めるのはやはり《若く可愛い女の子》がヒロインである映画か、あるいは《女性監督にふさわしい》と男性たちが考える種類の、子供向け映画などであり、大人の女性の現実を主題とした映画には誰もお金を出さない。 |
|
||
|
(3)それでも活躍する女性監督たち ただし、例外的な女性監督もいる。一つは、女優が監督するもので、これは気心の知れたスタッフや映画会社の応援を受けられるため、かなり多くの例がある。現在まで日本で長篇劇映画をもっとも多く監督した記録を持つ女性は、大女優だった田中絹代(6本)。 それ以外の《例外》は、残念ながら劇映画ではない。どうしても映画を撮りたかった女性たちは、日本では記録映画で優れた仕事をしている。もっと割のいい仕事につくチャンスのある男性たちがおき残した分野で、女性が入りやすかったためだが、女性たちは誠実に取り組み、世界的に評価される傑作を生んでいる。ただし、その多くは「男性と同じように仕事ができる」ことを証明するという姿勢で撮られ、彼女たちは女性であることを「克服」し、撮影現場では男性スタッフに女性として意識されまいとし、女性としての主題ではなく「一般的な主題」に目を向けた。そのため残念ながらこの分野で、女性の生き方を扱った傑作としては、羽田澄子の「AKIKO あるダンサーの肖像」くらいしかない。 8ミリやビデオによる短篇や実験映画の分野でも、女性の意欲的な活躍がある。これは腕力のない女性でも男性に頼らずに機材を扱えて、経済力のない女性でも無理なく作品を作ることができるためである。「清子の場合」でシモーヌ・ド・ボーヴォワール映画祭の奨励賞を授賞した出光眞子などが、フェミニズムの視点をもって国際的に活躍している。 現在日本で、もっとも痛快な《例外》は、ピンク映画の浜野佐知監督だ。彼女だけが、現在の日本のどの男性監督よりも多い映画を作っており、しかも現在その記録をどんどん更新しつづけている(おそらく300本近い)。ピンク映画というのは、男性の性的な欲望に応えるためのセックスシーンを多用した1時間ほどの成人向け映画で、いわゆるポルノグラフィー。だが日本では、全盛期を過ぎた映画会社が監督養成を止めたため、監督志望の優秀な若者たちがピンク映画で修業を積み、ここから「Shall We ダンス?」の周防正行など、優れた監督が輩出した。また、セックスの表現を武器として、社会の偽善的な秩序や禁忌に挑戦する意欲的な監督たちもいる。浜野は「男に選別され、その欲望に屈従する女性ではなく、自ら欲望する元気な女性のエロス」を描いて、業界屈指の人気を集めている。その実績をもとに、彼女は1998年、長篇劇映画として自ら長年あたためてきた「第七官界彷徨・尾崎翠を探して」の企画を実現した。この作品はまた、多くの女性たちのカンパなど、女性たちの応援によって作られた意義のある取り組みでもあった。 |
|||
|
(4)若手女性監督志望者の未来について 実は現在、ようやく日本でも女性が技術や教養を身につけて自己表現する生き方が広く認められつつあり、映画専門学校や各種映画講座などでは女性が男性より多くなっている。学生など若い映画作家志望者の登竜門である「ぴあシネマフェスティバル」の上位入賞者も、映画学校の卒業製作のコンペ受賞者も年によっては女性が男性を上回るようになった。彼女たちは、性的トラウマや家族の問題やレズビアニズムなどを、今まで男性監督たちが描かなかったような斬新なやり方で描き出す。ただし、今のところ、彼女たちに出資する製作者はほとんどなく、低予算の自主製作であるため表現に限りがあり、ほとんどが短篇で劇場にかけるチャンスもない(日本ではふつう短篇映画は映画館で上映しない)。だから女性監督の未来は決して楽ではないが、しかし、ここまで増えてきている女性監督志望者たちは、近い将来必ずある程度の成果を出さずにはおかないと思われる。 |
||
 |
| ■別表:最近日本で公開された女性監督作品(長篇劇映画のみ) | |||
| 作品タイトル | 年 度 | 監 督 | ジャンル・物語 |
| ぼくらの七日間戦争2 | 1991 | 山崎博子 | 児童向け・夏休みの冒険 |
| バカヤロー! | 1991 | 渡辺えり子 | 婚約者の好みに合わせてダイエットする女性の欲求不満。オムニバスの一編。 |
| 地球っ子、いのちと愛のメッセージ | 1993 | 槙坪多鶴子 | 児童向け・生命と地球を愛することを学ぶ。 |
| きこぱたとん | 1993 | 村上靖子 | 児童向け・伝統の風土が少女を癒す。 |
| ウィンズ・オブ・ゴッド | 1995 | 奈良橋陽子 | 特攻隊を通じて反戦を訴える。 |
| 風のかたみ | 1996 | 高山由紀子 | 平安時代の貴族の愛 |
| エコエコアザラク | 1996 | 佐藤嗣麻子 | 高校ホラー |
| 人でなしの恋 | 1996 | 松浦雅子 | 昭和初期の怪奇ロマン |
| 冬の河童 | 1996 | 風間詩織 | お互いに片思いする兄弟やその友人たち |
| デボラがライバル | 1997 | 松浦雅子 | 学園物・ゲイの青年と女子大生が恋のライバルになる |
| 萌の朱雀 | 1997 | 河瀬直美 | 過疎の村に生きる母と娘の恋 |
| ユキエ | 1997 | 松井久子 | 米軍人と結婚した日本女性の老い |
| わたしがSUKI | 1998 | 槙坪多鶴子 | 高校生の性を通じて自分の大切さを教える。 |
| 落下する夕方 | 1998 | 合津直枝 | 恋人に捨てられた女性が新たな人間関係の中で自分を取り戻す。 |
| 第七官界彷徨・尾崎翠を探して | 1998 | 浜野佐知 | 大正期の埋もれた作家の生涯とその作品世界。 |
| 老親(ろうしん) | 2000 | 槙坪多鶴子 | 自分を犠牲にして夫の両親を介護することに異義申し立てする女性の物語。 |
| LOVE/JUICE | 2000 | 新藤風 | レズビアンの少女と彼女が思いを寄せるノンケの少女との心の通い合いと揺らめき |
| DRUG GARDEN | 2000 | 広田レオナ | 神経症の女優と風変わりな人々 |
| ボディドロップアスファルト | 2000 | 和田淳子 | 理想の恋という幻想からの脱出 |
| 百合祭 | 2001 | 浜野佐知 | 老年女性たちのパワフルな性愛。恋の鞘当てを越えて。 |
| ダンボールハウス・ガール |
近日 公開 |
松浦雅子 | 全財産を失ったOLがダンボールハウス生活で人生の真実を掴む |
| *再録:2001年8月20日 |
| 【いしはら・いくこ】著書に、映画関連として『アントニオーニの誘惑』『菫色の映画祭-ザ・トランス・セクシュアル・ムーヴィーズ』『異才の人 木下恵介-弱い男たちの美しさを中心に』『イースト・アジア映画の、美』『映画をとおして異国へ-ヨーロッパ/アメリカ篇』。近刊『女性映画監督の恋』(8月末)。小説として『トリロジー 月の男』『月神祭』『彩の舞人- 新羅花郎伝承』。他に編書多数。 |
 |
 |
●日本海新聞2000年6月17日●尾崎翠 海越え羽ばたく 研究者が英訳、出版へ |
|
「第七官界彷徨」などの作品で知られる岩美町出身の女流作家・尾崎翠(1896ー1971)の作品が英訳されることが決まった。十四日に米国の大学の研究者が鳥取市を訪れ、尾崎の著作権所有者から許可を得た。出版を計画しており、尾崎作品が初めて海外に紹介される。 尾崎の作品を英訳するのは、米インディアナ大学で日本文学や日本語を教えている餘野木玲子さん(59)。十四日に鳥取市を訪れ、尾崎の親類で作品の著作権所有者の一人である松本敏行さん(68)や早川洋子さん(69)から英訳する許可を得た。 この日、同市職人町の養源寺にある尾崎の墓や文学碑を訪れた餘野木さんは「尾崎の作品は複雑で一口では言えない魅力がある。自分の経験を基にしていながら、私小説になっていない。“もう一人の自分”という概念を前面に出しているのは、当時の女性作家ではいない。『第七官界彷徨』はアメリカの学生に受けるのでは」と話している。 英訳する作品は未定だが、近く出版する計画。尾崎作品の英訳は、日本の大学で英語のテキストとして使っている例はあるが、出版されて海外で紹介されるのは初めてとなる。 尾崎は1920年代から30年代初期に特異な作風で注目された。その作品と生涯は「第七官界彷徨 尾崎翠を探して」として映画化され、国内外の映画祭で上映されて好評を得ている。 |
 |
|
『第七官界彷徨 尾崎翠を探して』上映委員会 |