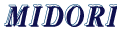
資料コーナー

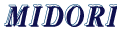 |
資料コーナー |
 |
●尾崎翠「地下室アントンの一夜」論● |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序 |
| 昭和六年に発表した「第七官界彷徨」で好評を得た尾崎翠は、心身の調子を崩したため に昭和七年九月、鳥取に帰郷した。翠は以後再び上京することなく、帰郷後にしばらく地 元の新聞・雑誌などに随想や詩を幾つか寄せたが、文学活動からは離れた。『新科学的』 昭和七年八月号に発表された「地下室アントンの一夜」は、彼女が帰郷前に発表した最後 の作品である。 この作品については、同名の人物が登場する「第七官界彷徨」「歩行」と関連して論じ られることはあっても、この作品単独で論じられることはなかった。これまでにこの作品 が論じられる場合においては、稲垣真美氏、加藤幸子氏から「歩行」の創作ノート、解説 版であるとの意見(注1)、また戸塚隆子氏からは〈地下室アントン〉において、リアリ ズム対超現実主義の問題が融合する理想郷を見いだすという解釈(注2)が提出されてき た。論者はそれらの意見に賛成する者ではない。「地下室アントンの一夜」を「歩行」の 従者とする根拠を稲垣、加藤両氏は明確に提示されてはいない。また戸塚氏の解釈は、作 品中の「詩人」「動物学者」といった表層的な人物設定に牽かれた図式的な解釈であり、 「地下室アントンの一夜」の作品解釈にはなお余地があるだろう。 本論文では「地下室アントンの一夜」を、他作品との関連にとらわれることなく、独立 したひとつの作品として、解釈し、論じる。 なお、この作品には幸田当八、土田九作、動物学者松木という主要人物と、小野町子、 松木夫人を含めた五人の登場人物があらわれるが、論者はこれらの登場人物らは土田九作 ひとりの内的な要請により、彼の心のなかで創出され想像されたものであると考える。こ のような読解に至る考察を提示することが本論文の目的とするところである。 |

|
第一章 「(土田九作詩稿「天上、地上、地下について」より)」の性質 |
|
|
| 「地下室アントンの一夜」という作品は、「(幸田当八各地遍歴のノオトより)」、「(土田九作詩稿「天上、地上、地下について」より)」、「(動物学者松木氏用、当用日記より)」、「(地下室にて)」の四つの部分から成り立っている。(以下、各部を「当八ノオト」「九作詩稿」「松木日記」「地下室にて」と略称する。)ただし部分は均等ではなく、この作品のおよそ三分の二を「九作詩稿」が占めている。「九作詩稿」は一人称「僕」(注3)によって語られる詩稿である。これは「詩稿」であるので、作者「土田九作」と語り手「僕」は別個のものと考える。 「九作詩稿」は題の示すとおり「天上」「地上」「地下」について述べられている。「九作詩稿」についての考察が第一章の目的であるが、三つの各部分についての特徴を順に考察していく。 なお作品全体の冒頭は「当八ノオト」であるが、この部分についての独立した章は設けず、第一章第四節にてあわせて考察する。 さて「九作詩稿」は、「天上、地上、地下について」と題されているが、「地上」「地下」について述べる部分には、「地上は、常に、決して空ほど静かではないやうだ。」、「地上には、略以上のやうな事物があつた。そこで後にのこつてゐるのは地下の問題だけだ。」とそれぞれに「地上」「地下」について述べるという表示があるが、「天上」についてはそれは無い。「天上」について述べていると見なされる部分は、「空には、太陽、月、その軌道などを他にしてなほ雲がある。」と始まる「九作詩稿」の冒頭から「── 空の世界はいつも静かであつた。」と終わる部分までである。この詩稿そのものは「(土田九作詩稿「天上、地上、地下について」より)」という、「より」と示されるように引用であるから、詩稿の冒頭にあたる「空には、太陽、月、その軌道などを他にしてなほ雲がある。」より前の部分に、「天上には」と述べている部分があるかもしれない。ただしそれは本作品「地下室アントンの一夜」においては不明である。ただ「空」について述べている部分は、「地上」について述べている部分とは、詩稿の作者九作の、以上のような表示によって明確に分けられていることを確認しておきたい。本論では「地上は、常に、決して空ほど」以前の部分を「天上」部、この部分以降、「地上には、略以上のやうな事物があつた。」の直前までを「地上」部、「地上」部以降を「地下」部と呼称する。 「天上」部は、客観的に「空」に存在する事象について述べ、それらについての感想を述べるというスタイルをとっている。ここで述べられる感想とは、詩稿の後続部分の「地上」部のように「僕」自身の内面に具体的に立ち入ったものではない。しかしこの「空」の事象についての感想である「雲」に関する言及と「耳鳴り」という聴覚の異常についての言及は本作品において重要な部分であり、それゆえ「天上」部は作品の部分としては僅かであるが、作品全体に対する影響は大きいと論者は考える。「雲」に関する言及、聴覚の異常については第一章第三節にて検討、考察を試みる。 |

|
|
|
「地上」部は
まず、松木に対する敵対心から見ていきたい。 |
||||
|
|
 |
| 1における日よけ風呂敷、2におけるおたまじゃくしとの、「僕」とのスピリット上での一体化を、詩人である「僕」は主張するのだが、それを松木は認めない、と設定し、思いこんだところから、「僕」は松木へ攻撃を向ける。「僕」は松木とその妻について「彼等はつねに僕を曲解してゐて、正しい理解をしようとはしない。」と不満を抱いているが、それは「蔭ながら」思っているだけであって、彼らに不満を直接向けているわけではない。「僕」の松木への攻撃の根拠でもある、「僕」の「烏は白い」という詩をみて松木がひどく怒ったという件についても、直接にその不満を松木へ向けていない。直接に対手に向かわないいらだちは、対立感や反撥心を増幅させてゆく。1においては単に不満、反撥を述べているだけである。それでも「おたまじやくしのみなもとは蛙の卵であつて、はてしなく、雲とつづいた寒天の住ゐの中に、黒子のごとく点在してゐる。」と喩的表現を用いて「おたまじやくしは蛙の子であるといふ」以外の理解の仕方を示していながら、それについての主張へ向かうのではなく、「どの三十ミリメエトルを切りとつてみても、その模様は細かいさつま絣の模様にすぎない。」という比喩から続く発想で、「何と割切れすぎる世界だ。動物学者の世界とは、所詮割切れすぎてぢきマンネリズムに陥る世界にちがひない。」と、自らの、世界に対する詩的理解を示して動物学者松木へ対抗しようとするよりも、松木に対する抑圧されているいらだち、松木をただ否定する感情を示す方が勝ってしまっている。さらに2においては、松木に対する反撥心、攻撃的感情は「殴りたくなつてしまつた」という段階まで発展する。これは、突然このような感情が出現したというよりも、松木に対する否定的な感情が繰り返されたからこそ、このように直接的な攻撃のかたちを想定するまでに発展したのだろう。 次に、松木に対する恐怖心について見ていきたい。 |
|
|
 |
|
| 「僕」には4のような「木犀の花さく一夜」の体験が先行して存在していて、松木氏の著書の題を知ったのはその後と思われる。それゆえ「僕」は、松木が自分の恋について著書の題において言い当てていると思い込み、松木に自分の心が知られているという妄想を持ってしまう。3において「僕」は松木を「心理透視者」「怪物」「不死鳥の心臓」と符牒し、恐怖心をいだき、それが高まるにつれて呼称を「松木氏」から「あいつ」と蔑称に変化させ、その恐怖心に打ち勝とうととする。しかしみずからの妄想に圧倒された「僕」は松木に対して降参し、松木にたいする呼称も「松木氏」「あなた」という敬称へ変化する。5においても同様に、「松木氏」→「あいつ」→「松木氏」と呼称が変化する。 3、5での松木に対する恐怖心との戦いとそれに対する屈伏は、先に確認した松木に対する敵対心とその増幅とともにこのように繰り返し出現する。5において「僕」は「小野町子は、もう失恋から治つたであらうか」と考え続けていて、ここで考えるのを止め、「僕」自身の思考も「地上」の問題から「地下」へと移る。しかしここで「僕」が「地上」の問題を考えることを止めなかったら、小野町子について考え続けるのと同時に、松木に対する以上のような妄想も引き続き繰り返し、円環を描くかのように出現したであろう。 「九作詩稿」は「僕」という一人称で語られ、そこには松木を相対化する視点は設けられない。ここで語られる松木とはあくまでも「九作詩稿」中の「僕」が想いえがいた松木であり、「僕」が創り出した仮象としての人物である。「九作詩稿」において松木は、詩人である「僕」の視点からの否定されるべきありかた、それゆえむやみな攻撃心を向けることが可能である人物として設定、形象されるが、松木は実体のない仮想敵である。そのため形象された松木に向けられた「僕」の攻撃的で否定的な感情は、今度は相手である松木が「僕」自身の心理を「透視」し「言ひ当て」ているという妄想となって、「僕」自身を苛むものとして還ってくる。「僕」自身の攻撃心が、「僕」が形象した仮象としての松木へ向かう限り、このように「僕」を苛ませる妄想は消えないだろう。 |
 |
|
|
| 「地上」部において、松木が媒介として「僕」にもたらしたものは、「人工孵化のおたまじやくし」と「小野町子」の二つである。松木を媒体としてもたらされたこの二つは、「僕」の心のありように大きな影響を与えるのであるが、第三節では「僕」の心をとらえたこの二つについて考察する。 |
|
|
|
|
 |
| まず「九作詩稿」における「僕」が「おたまじやくしの詩」を書きたいと「切に願望」し、「おたまじやくしのことばかし考へ込んでしま」うことについて考察する。 ここで「僕」の耳鳴りについて確認しておきたい。 7のように、「僕」は耳鳴りに正常な聴覚を侵犯され、聴覚に異常をきたしている。そして「何といふ愚劣な頭だらう。」と述べているように、もちろん聴覚の異常を歓迎しているわけではなく、その状態に苦痛を覚えている。またこの耳鳴りは南風に反応して起こるものであるので、「僕」自身は全く耳鳴りのしない快適な状態をも知っている。このような状態にある者が望むことは、やはり正常な状態に聴覚が回復することであろう。 ここで「おたまじやくしの詩」について、「おたまじやくし」=音譜として、視覚化された音のイメ-ジとして考えてみると(注4)、「おたまじやくしの詩」とは「音譜の詩」であり、「音譜の詩」とは音楽のことではないか。ならば聴覚の異常を補完するものとして「僕」が「おたまじやくしの詩」=音楽を願望するのは当然である。詩人とは言語を用いて表現する人間だが、言語、言葉とはそもそもは声であり、声はそもそも音である。音の感覚をつかさどる聴覚に異常をきたすということは、詩人にとっては根幹的な部分にダメ-ジを受けるにほかならない。 また、正常な状態の聴覚がどのようなものであるのかを「僕」が知っているのと同様、「おたまじやくし」というものがどのようなものであるのかを、視覚などの感覚として「僕」は既に知っていて、そこから「僕」は「詩」を作ろうと出発しているのだろう。さて感覚とは、その個体の外部である表層が環境と接触した場合におこる内側からの反応だとし、それが内側に沈潜し形となることを印象とし、「詩を書きたい」ということは「詩」としてあらわしたいと想定する独自の印象について、言語を用いて創作し、外部へ表現したいということだと換言してみる。そうすればこの場合、「僕」にとっては、「おたまじやくし」というあるひとつの印象を外部への表現としてつくりあげている最中、それが書けようかという折に、松木から届けられた人工孵化のおたまじゃくしを見て、創作を邪魔する新たな感覚をはからずも得たために、一からやりなおして、つくりなおさなくてはならない羽目になったということだろう。それゆえ「僕」は4のように、「おたまじやくしの詩を書かうとするとき実物のおたまじやくしを見ると、詩なんか書けなくなつてしまふんです。小野町子が季節はづれの動物を僕の机の上に置くと同時に、僕はもう、おたまじやくしの詩が書けなくなつてしまひました。僕は大きい声で告白しなければなりません。僕は実験派つてやつではないのです。僕はほかのものです。」と述べるのではないだろうか。 ところで、聴覚は感覚のひとつであり、それは「僕」という個体の生存率を高めるには無いよりはある方がよい。聴覚に異常をきたしているということは、「僕」は標準の状態よりも生存率が低下していて、生の状態よりも死へと少しでも近しい。8より、聴覚のみが原因ではないかもしれないが、その季節の空模様の憂鬱さが象徴するような、「死ぬ考へ」と、「おたまじやくしの詩」を書きたいと「切に願望」することは同時に起こっている。「おたまじやくし」は喪失されている正常な聴覚を補完する形象であり、またその季節に地上に発生、誕生する生命体でもあることから、死を求めるベクトルと「おたまじやくしの詩」を求める、生を求めるベクトルがなんとか均衡を保って「僕」の生命を地上に留めていたのであろう。 次に、「僕」が小野町子に心をとらわれて、小野町子のことを考え続ける(5参照)ことについて考察する。 小野町子は「ひどく鬱ぎこんだ一人の女の子」であり、「僕」からは「ひと目見て失恋者」という属性を付される。町子は「僕」の前で「溜息」を吐いただけであるが、「僕」が町子に「心情を因へ」られるのは彼女の溜息が「微か」だと「僕」にみとめられるものであったためである。「僕」はその「微か」さを生じた源泉である町子に「心情を因へ」られ、「恋」をする。町子は雲が雨を生じるように微かさを生じ、「僕」の心に変化を与える。 町子が「人工孵化のおたまじやくし」を持って「僕」の前に訪れるまでは、「僕」は「おたまじやくし」に心をとらわれていて、しかも「おたまじやくしの詩」が書けそうだ、という状況であった。前述のような「おたまじやくしの詩」を書くことが不可能になったことと、それと同時に僕が町子に心をとらわれたことが起こったのは、「僕」自身に「とらわれたさ」とでもいうべきものが存在していて、「僕」の「とらわれ」の対象が、もはやとらわれることが不可能となった「おたまじやくしの詩」から、町子へと移動したのではないかと論者は考える。 ところで「僕」の小野町子へのとらわれは9などのように、「恋」または「片恋」と表現される。しかし5に「恋とは、一本の大きい昆虫針です。針は僕をたたみに張つつけてしまひました。僕の部屋はまるで標本箱です。箱の中で、僕は考へてゐるんです。あの夜の誰かに失恋をして溜息ばかり吐いてゐた小野町子は、もう失恋から治つたであらうか。それとも…………/しかし僕はもうよほど疲れたから、その続きを考へることを止さう。考へ続けてゐると、だんだん、女の子が失恋から治つてゐない気がして来て、おれは悲しくもなるんだ。」とあるように、「恋」を「小野町子が失恋から治ったかどうか」という「謎」にとらわれることと表している。 この場合、「謎」の回答を出すために必要なのは、回答を創作し、外部へ表現するという作業である。 「おたまじやくしの詩」の場合には創作の最中に邪魔が入ったかたちになって、「僕」はとらわれから脱出できなかった。しかし今度の「小野町子が失恋から治ったかどうか」という「謎」については、そのような邪魔は入らない。それなのに「僕」は謎に回答を与えるための情報収拾をするなど具体的な行動にうつりもせず、「謎」を解くために何をすればよいかも考えない。「僕」は9にあるように「それつきり小野町子に逢ふこともなかつた」のである。「僕」は答えの出ない「謎」へとらわれることを自ら望んでいるかのようである。 「回答の出ない謎」にとらわれるという状態は、回答の出ない状態から出る状態へとうつる合間における、苦痛ではあるが一種の安定した状態である。ここで謎がとけることによる状態の変化について、それが耐えがたい苦痛かもしれないという可能性を想定するならば、たとえ苦痛であろうと耐えうる苦痛にとどまるという選択をし、謎がとかれることを本気では望まないという場合がある。また、「耐えうる苦痛」が「耐えがたい苦痛」にまで嵩じた場合、残された手段は「回答を出すため謎をときにいく」ことであるが、「あの夜の誰かに失恋をして溜息ばかり吐いてゐた小野町子は、もう失恋から治つたであらうか。」「考へ続けてゐると、だんだん、女の子が失恋から治つてゐない気がして来て、おれは悲しくもなるんだ。」とあるように、「僕」は町子の治癒に対して悲観的であり、耐えがたい回答を得るよりはむしろ、「謎がとかれていない」という状態へ留まるほうを望んでいるようである。 しかし仮に「僕」が小野町子に逢いにゆき、小野町子自身が「わたしは失恋から治ったのだ」と主張し、その回答がたとえ事実であっても、その謎の回答が「僕」に納得がいくかどうかという問題がある。その回答を納得するのは「僕」自身である。「僕」が「小野町子は失恋している」と思いこみたい限りは、「小野町子が失恋から治っていない」という状態は、「僕」の精神の内において継続される。 以上、「僕」に在る「とらわれたさ」について考察してきたが、「地上」にいる「僕」は「疲れ」るまで、「とらわれているもの」について考え続けることを、みずから止めることができない。「僕」がとらわれているものは、「すがるよりどころ」としてまるで「僕」の精神の根底を支えているかのようである。「すがるよりどころ」は「おたまじやくしの詩」であったり「小野町子が失恋から治ったかどうか」であったり、その発露の仕方は固定せずに流動性をもつが、それが「僕」の自己の基盤の根底的な部分の不安定さを示していることには変わりない。この原因は、もともとは以上のように「僕」の身に沿って存在していた健康な聴覚の喪失に始まり、それらへ「とらわれる」ことが、健康な聴覚を喪失したことの補完となっていることである。原因となるものは主体の側に内包されているということである。 ここで、冒頭の「雲」についての考察を述べておきたい。6の「九作詩稿」の冒頭には「空には、太陽、月、その軌道などを他にしてなほ雲がある。雨のみなもともその中に在るであらう。」とある。「なほ雲がある。」と述べられるように、「雲」とは空を眺めた時に、存在する場合と、存在しない場合とがある。この詩稿の場合は雲が存在している場合の空であるが、それによって、「層雲とは、時として人間の心を侘しくするものだが、それはすこしも層雲の罪ではない。罪は、層雲のひだの中にまで悲哀のたねを発見しようとする人間の心の方に在るであらう。」という感想が導き出される。これは、雲を眺める主体である人間の側に、「悲哀」などの何らかの感情を求めようとする態度があるから、眺めた対象である雲から、求めたような感情を導き出すことになるということだが、ここでも、現れる結果には原因があり、原因は主体の側に内包されている。このように、「天上」部の「雲」についての「僕」の述懐は、「僕」の健康な聴覚の喪失についての比喩となっている。 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
| 「地下」部において、「僕」は「何処かの医者」の「遍歴ノオト」のアレンジによって「地下室アントン」を発想し、そこへ向かう気持ちであることを表明する。本作品中において「九作詩稿」の引用は12でおわり、「九作詩稿」に、この12の続きが存在するかどうかは不明である。もっとも、「天上」部の冒頭より前の部分、「地下」部の後続部分が仮に存在するとしても、本作品にはその引用が必要なかったのではないか。必要ならば作中に書かれているだろう。 「僕」が地下を志向するのには11のように、「何処かの医者」の「遍歴ノオト」の影響を受けている。作品の冒頭部である10「当八ノオト」と「遍歴ノオト」は同一の文面である。しかし10には「医者」の「遍歴ノオト」であるとは書かれていない。また、幸田当八は「(地下室にて)」の部分においては、「心理学徒」という名称で語り手「私たち」によって紹介される。ここでもやはり当八は「心理医者」ではない。当八は作品中ではっきりと「医者」と明示されず、その意味では明確な「医者」の属性を帯びない。しかし、13「地下室にて」において当八は、「心理病とは殖える一方のものです。」と言い、「病」に関わりその知識を持っていることが示される。ここで「幸田当八」は「医者」と見なされ、同一の文面のノオトを所持している幸田当八とこの「何処かの医者」は同一人であると確定し、このノオトもまた同一のものであると確定してよいと論者は考える。 そう考えると、「当八ノオト」は「九作詩稿」に引用されていると考えられる。ただ、「九作詩稿」においては、「僕」の知識として「何処かの医者」の「遍歴ノオト」が存在していることのみを示していて、幸田当八の名前は現れない。 しかし、「九作詩稿」の作者である土田九作自身は、自分とはまったくの他人として存在している幸田当八の「遍歴ノオト」を読んでいるか、また「遍歴ノオト」の書き手が幸田当八であり、しかも彼が「医者」であると知っているのだろうか。「九作詩稿」中のみならず作品中にも、その情報はもたらされない。それゆえ「九作詩稿」における「遍歴ノオト」と、またそれと同一とみなされる「当八ノオト」は、土田九作自身の創作であるとも解釈できる。となれば、「幸田当八」は松木同様、土田九作自身が創出した、九作の仮象のひとつであると解釈できる。この解釈を試みると、「九作詩稿」内で引用として指示されている「何処かの医者」の「遍歴ノオト」の部分は、本作品全体の冒頭に、抜き出して配置されているということになる。 「何処かの医者」の「遍歴ノオト」の部分が作品全体の冒頭に、抜き出して配置されるほど重要さを担わされたのは、作品の題名にもあらわれる「地下室アントン」の発想に関わったからでもあろう。 さて、作品内で「医者」と明確に名指されるのはアントン・チエホフのみである。医者とは、なんらかの不健康、病気である状態で苦しんでいるものを苦しまなくてよい状態へ向けて治療する者だと考えると、「僕」は以上見てきたとおり、明らかに治療を、それをほどこす医者を必要としている者である。そして、11「帳面の言葉」にあらわされる心理状態は、それを書いた医者によれば「心理病院に入院しなければならない心理状態」であり、この言葉に賛成している「僕」は、入院が必要な者でもあろう。しかし「僕」は、心理医者が「勝手にいろんな心理病を創造するから、それにつれてそんな病人が出来てしまふ」と考えている。この心理医者から見ると自分が病人であることを「僕」は知っている。そこで、医者から入院を強請されたら、「どこかの地下室に逃げてやらう」と考える。この「帳面」を書いた医者に対して「僕」は反撥をおぼえている。その一方で、「むかしアントン・チエホフといふ医者は、何処かの国の黄昏期に住んでゐて、しかし、何時も微笑してゐたさうだ。僕の地下室の扉は、その医者の表情に似てゐてほしい。地下室アントン。」と述べているように、「アントン・チエホフといふ医者」に対しては親和的である。 「僕」は「地上」からの場所の移動として、自ら望んだものではない、「強請」された「入院」ではなく、自ら望んだ「地下室」への逃避を希望する。「僕」は「地下室」の扉について、「うんと爽やかな音の扉」であり、「むかしアントン・チエホフという医者は、何処かの国の黄昏期に住んでゐて、しかし、何時も微笑してゐたさうだ。僕の地下室の扉は、その医者の表情に似てゐてほしい。」との二つ、いわば喪失されている聴覚とアントン・チエホフという医者の微笑をもとめている。「僕」が「地下室」を発想するには、反撥をおぼえているにせよ、「何処かの医者」の「遍歴ノオト」から触発されたものであり、また、発想した「地下室」に居るのも「医者」であるアントン・チエホフである。「僕」は「地上のすべて」、聴覚の異常とそれに端を発する苦痛と悲しみ、を忘れることを希望して、治療者である「医者」をもとめるために、「地下室アントン」を発想した。 |
 |
|
『第七官界彷徨 尾崎翠を探して』上映委員会 |