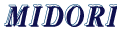
編集後記

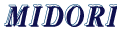 |
編集後記 |
 |
|
●失われた(?)2003年のこと● |
||||||||||
| -鴨ヶ磯・『尾崎翠集成』・『臨床文学論』・ 『読む女 書く女』・「尾崎翠の病跡」など- |
||||||||||
♪ わたしは02年で燃え尽きてしまったのだろうか? 編集後記を書くのは、実に02年9月以来だ。この時の更新で、塚本靖代さん・石原郁子さん・矢川澄子さんの追悼を書き、筑摩版定本全集に新しく収録された翠の作品への疑念を書いた。わたしのHPの時間は、そこでピタリと止まってしまった感がある。追悼の思いも、稲垣氏のまやかしへの怒りも、全然古くならず、時間は止まったまま、瞬きする前のことのように新鮮に生き続けているのだが-。稲垣×筑摩ラインを相手にいくら疑問を投げかけても、何も返ってこない。いっそ名誉毀損で裁判にでも訴えてくれた方が、白黒決着がつくのだが、岩波新書「ワインの話」問題の時も、トボケて無視を決め込んだ稲垣氏だからね。 この間、わたしは何をしていたのだろう。03年のフォーラムにも参加できず、目先の必要に追われた更新しかできなかった。02年の暮れには、石原深予(みよ)さんから「文献目録」の追加データを頂いていたのに、今回ようやく更新するというテイタラクである。深予さんの目が覚めるような「地下室アントンの一夜」論を、資料コーナーにアップできたことが、昨年唯一誇れることだったろうか。難解な論文を、明快にレイアウトした鈴木裕子さんのデザイン思想と技量には、あらためて惚れ惚れする。何度見返しても、美しく合理的だ。深予さんが「柔らかな色調とバランス…一見、拙論が『難解』に見えないところがスバラシイ」と笑い喜んでいた。 そう言えば、近年短歌を詠んでいる深予さんが、短歌季刊誌『霹靂(かむとき)』16号で短歌を発表すると同時に、折口信夫と尾崎翠を比較対照した書評を書いている(『薬と毒-穂積生萩『私の折口信夫』を読む』)。まるで土田九作が書いたような愉快な書評だが、折口の読者にはいささか刺激が強いかもしれない。短歌の中から、三十首中、最後の作を紹介しておこう。わたしは意味が分からなくて、メールで問い合わせました。 わたしたちはともにすぐさむありうべき蘚になりても骨になりても また、鈴木裕子さんは最近、女性の暮らしと地域情報のサイト「コム・サポート」を立ち上げた。健康や生活の情報とともに、ネット・ギャラリーを設けて女性写真家の作品などを紹介している。また、個性的な活動をしている女性を取り上げるコーナーでは、浜野佐知監督も丁寧に紹介して頂いた。女性・男性問わず、ぜひ一度訪問してください。
♪ 愚痴を続ける。02年末に出た筑摩書房の文庫版『尾崎翠集成』上下巻は、はなはだしく期待を裏切るものだった。「中野翠編集・解説」というのが謳い文句だったので、大いに期待する一方、「オッサン、よく自分の手から放す気になったな」というのが正直な感想だった。かつて創樹社版のアンソロジーを出す時、山田稔さん一人の解説のはずだったが、稲垣氏が自分をないがしろにして翠の本を出すとは何事かと強引にネジ込み、やむなく二本立ての解説になった経緯を、玉井五一編集長に聞いていたからだ。 ところが筑摩の『集成』、実際に出てみると、版面(文字を印刷する範囲)はページ目いっぱいの上、書体や印刷にムラがあり、読みにくいことおびただしい(下巻では直っている)。また、中野翠さんの「編者後書き」では、わたしたちの映画を『尾崎翠の世界』と誤記し、監督名もクレジットしない。その上「稲垣眞美さん」を「この人こそ作家・尾崎翠に関するもっとも詳細厳密な研究者ではないだろうか。筑摩書房版の全集(上下巻)には、たいへん充実した解説が寄せられている」と最大級に持ち上げている。あの長いだけで放漫、恣意的、重要な部分に捏造や妄想を含む「解説」の、どこが「充実」していると言うのか。これはもしかして、稲垣氏が編集や解説から外されることをゴネて、やむなくこういう措置がとられたのかとも思ったが、署名原稿である以上、中野翠さんの正直な考えと受け取るべきだろう。さすがは反時代、反フェミで、オヤジに好かれる「女流」評論家だけのことはある。 この後書きにも目立つ誤植があり、杜撰な作りに加えて浜野監督から映画のタイトルの誤りに関する猛抗議(?)も受けて、結局上巻は刷り直したとか。もっとも、第一刷を回収したわけではないので、おそらく名目上の少部数に違いない。筑摩書房は、個人全集や個性的な文庫が充実した良心的出版社と思われているが、尾崎翠の定本全集や今回の『集成』に限って言えば、カバーだけはそれらしく作って、中身は何でもいいというポリシーらしい。そうだ、この間に最初の全集を出した創樹社は倒産したのだった。尾崎翠全集を、私利私欲から筑摩にトレードした稲垣氏あたりは、先見の明を誇っているかも知れない。  ♪ 「しかし、悲観しない方がいいね」(三五郎)。昨年は良いこともあったのだ。以前、精神病理の立場から独自の尾崎翠論「匂いとしての<わたし>-尾崎翠の述語的世界」(97年『日本近代文学』)を書いた近藤裕子(ひろこ)さん(現・東京女子大助教授)の著書『臨床文学論-川端康成から吉本ばななまで』が、ついに上梓された(彩流社刊)。数年前から博士論文が単行本になると聞いていたのだが、札幌大学に赴任中に出版されたのだ。 ♪ 「しかし、悲観しない方がいいね」(三五郎)。昨年は良いこともあったのだ。以前、精神病理の立場から独自の尾崎翠論「匂いとしての<わたし>-尾崎翠の述語的世界」(97年『日本近代文学』)を書いた近藤裕子(ひろこ)さん(現・東京女子大助教授)の著書『臨床文学論-川端康成から吉本ばななまで』が、ついに上梓された(彩流社刊)。数年前から博士論文が単行本になると聞いていたのだが、札幌大学に赴任中に出版されたのだ。近藤さんには『第七官界彷徨・尾崎翠を探して』の岩波ホールでのロードショー時に、『読書新聞』に素晴らしい映画評を書いて頂き、『百合祭』完成時には札幌から支援を受けたこの映画の先行上映を、地元で観て頂き、パンフレットに感想をお願いした。翠の関係で知り合った方々とは、不思議につながっていく。今回の『臨床文学論』は、すぐに朝日新聞の書評欄で取り上げられ、池上俊一・東大教授(中世の魔女研究がとても面白かった)が、次のように書いている。 「今、臨床文学の種が播かれた。病める現代日本において<わたし>が溶解してゆく危機の諸相を、ぎりぎりの言葉で表現する現代作家たち。彼らの特異な訴えに注意深く耳を傾け、『時代の病』へと開いてわたしたちに仲介する姿は、託宣をする巫女のようだ」 川端康成と尾崎翠以外は、すべて現代作家(吉本ばなな・村上春樹・山本昌代)だが、近藤さんにとっては二人とも優れて現代文学の作家であるらしい。前書きで次のように記している。 「現代にあって、病いはもはや『特別な事態』ではない。(中略)そもそも病いとは自己性そのもの、<わたし>という現象そのものなのではあるまいか。本書はこうした自己危機・自己溶解というものが、どのような出来事として生起するのか、言い換えれば<わたし>という幻想が何によって支えられ、どのような系に開かれ/閉ざされているのかを、現代文学というテクストに拠りながら解き明かそうと試みたものである」 書くことを断念するに至った翠の病いが、いったい如何なるものであったか、かつての70年代風、狂気をめぐる俗流のロマンチックな思い入れではなく、専門的な見地から精密に検討される時期に来ているのだろう。すでに「匂いとしての<わたし>-尾崎翠の述語的世界」を読んだ読者も、本書のパースペクティブにしたがって再読すると、新たな視角が開けてくるに違いない。 近藤さんは、昭和3年の「山村氏の鼻」から昭和7年の「地下室アントンの一夜」に至る、翠の代表作のす べてによって「尾崎翠の嗅覚イメージの生成と消長を辿ることができる」と言う。「山村氏の鼻」では 「臭いとなって漏れ出てしまう否定的な<わたし>というモチーフが潜在」したが、「木犀」では芳香が 女主人公と「世界との関係をひととき調和的なものに変える役割」を果たし、「第七官界彷徨」に至って 「嗅覚はことに聴覚と共鳴しながら芳醇で複合的な感覚世界を展開する」。しかし「こほろぎ嬢」になる と再び暗雲が漂い始め、桐の花の匂いは、こほろぎ嬢を「衰弱させ、ますます神経の病いへと追い込んで ゆく」。こうした「<匂い>の見取り図」にしたがって、近藤さんは「なぜ<私>の衰微は、とりわけ嗅 覚に沿って語られねばならなかったのだろうか」と問う。 <匂いとしてのわたし>というテーマについては、実際に読んで頂くとして、もう一方の「述語としての<わたし>」とは何か? 「こほろぎ嬢」の場合、外出しようとする嬢は「桐の花の匂ひ」を吸い込みながら、一方でそれを何とか食い止め、吐き出そうとする。なぜなら桐の花は「くたびれている」(述語)からで、くたびれた匂いを嗅ぐことで、嬢自身もくたびれてしまうのだ。 「このような述語レベルの同化作用によって、『桐の花の匂ひ』と『こほろぎ嬢』という主語(主体)同士も限りなく近づいてゆく。つまり異なる主語の述語レベルでの同一化が、主体の境界を溶かし、両者を癒合させてゆくのである。他との明らかな差異が自己性を成立させる条件だとしたら、『こほろぎ嬢』の<わたし>は、きわめて危機的な状況にあると言えよう」 翠の作品における<わたし>が、いわゆる西欧的自我とまったく違っていて、その揺らめくところにわたしは魅力を覚えるものだが、近藤さんの指摘する「述語の同一性に基づいて本来別個の存在を同一視してしまう」「述語論理」は大きな役割を果たしているようだ。「主体の危機」はマイナスだけでなく、 「世界に向かって自己を開き、世界の諸物(諸現象)と入り交(か)うことこそが<世界内存在として生きる>ことだとしたら、他との境界を固持することは、かえって自己を囲い込み、息を封じることになる」 ピンチに瀕しながら、その一方で「さまざまな音や匂いを呼び寄せ、見えない世界の豊かさを開示」したのが、翠の<わたし>だった。 また、「こほろぎ嬢」に登場する「私たち」と「自称する不思議な語り手」についても、「ゆるやかなまとまりのうちにひとつの物語を紡ぎ上げてゆく語りの主体(「私たち」)は、単一の中心を持った複数の主体というより、複数の中心をもったひとつの主体というほうがふさわしい」と指摘する。「複数の中心」というと、反射的にわたしは花田清輝の「楕円の思想」を思い浮かべてしまうが、翠の場合は「まくろうど嬢」を人格内に共存させる「しやあぷ氏」も含め、「多重的自己像」なのだ。久々に近藤さんの論文を読み返しながら、尾崎翠における<わたし>について、改めて示唆されるところが多かった。 ♪ 近藤裕子さんはまた、『國文學』2003年4月号「モダニズム的表象」特集にも「尾崎翠『歩行』の身体性-風とお萩とおたまじゃくし」を寄稿している。この論文では、『第七官界彷徨』で断念した「円形構造への未練」が『歩行』で「再試行」されているとして、目的のかなわない歩行、恋の秘密にも似た柿の実を一緒に食べること、幻想によって浮かび始めた町子の心身を、地上へ引き戻そうとする祖母のお萩、歩く町子の周りを絶えず吹いている風と、瓶に詰められたおたまじゃくし(=音符)の関係などが、魅力的に分析されている。わたしは特に、柿とお萩の対照に強く心惹かれたが、この柿の木は今でも、翠フォーラム代表の土井淑平氏宅の畑に健在なのですね。今年の文学散歩ツアーでは立ち寄るのでしょうか? ♪ 昨年の尾崎翠フォーラム2003の文学散歩ツアーには、なんと川崎賢子さんが参加されていた。川崎さんは、これまで何度も尾崎翠を論じてきたが、わたしには02年の11月に聞いた「岩波市民セミナー 『尾崎翠』を読む」が忘れられない。受講できたのは、全4回のうちの第3回目だけだったが、セミナーの通しタイトルは「恋するテキスト-尾崎翠的世界におけるセックス/ジェンダー/セクシュアリティ」。第1回目のサブタイトルなんて「あぶなくて、きわどい<尾崎翠>」ですからね。すっかり嬉しくなってしまいました。  わたしが聞いた第3回目でも、インセスト・タブーと家父長制の崩壊、蘚やおたまじゃくしなど、人間外のものにエロスが過剰に表現され、翠の「恋するテキスト」では異性愛が適用できない・セックスとジェンダーの二項対立を超えた翠のユートピア的エロス、等々刺激的な分析が速射砲のように繰り出され、茫然としながらも心地よい音楽を聴くようだった(十全に理解できなかった傍証? いやいや、眠ったわけではありません)
わたしが聞いた第3回目でも、インセスト・タブーと家父長制の崩壊、蘚やおたまじゃくしなど、人間外のものにエロスが過剰に表現され、翠の「恋するテキスト」では異性愛が適用できない・セックスとジェンダーの二項対立を超えた翠のユートピア的エロス、等々刺激的な分析が速射砲のように繰り出され、茫然としながらも心地よい音楽を聴くようだった(十全に理解できなかった傍証? いやいや、眠ったわけではありません)このセミナーをもとに、岩波から単行本が出ることになっているが、その前に02年『読む女 書く女-女系読書案内』(白水社)が出版された。87人の女性の作家、劇団、少女マンガ家、詩人、歌人、俳人、評論家、研究者などが、多彩に取り上げられている。そのなかで尾崎翠と「花束」がピックアップされているのだが、どうして「花束」? この本のもとになったのが『静岡新聞』の読書欄の連載で、テーマは「女性作家によるここ百年の恋愛小説を読み直す」だった。各作家とも、必ずしも代表作が取り上げられていないのはそのためで、川崎さんは翠の「28歳の習作」を、セクシュアリティとの関わりで次のように読む。 翠の作品に特徴的な「追憶の溜息」を吐くヒロインは、船上の若者に誘われるが、甲板に上がって行こうとはしない。それは「ちょっと自分をつついた感情」(尾崎)が「性的な存在に彼女を変えうる感情であると、気づいている」(川崎)から-。船員は代わりに、彼女の持っていた野草の花束を請う。彼女は財布に使っていた黒いリボンで結びなおし、甲板に投げ上げる。花束に接吻し、「ありがとう、あなたのリボン!」と言う若者。川崎さんは、このやり取りを「すれ違い・交換・転移」と解する。 ヒロインと「交換」された花束、それがさらに「転移」して黒いリボンとなるところなど「習作」どころか、まさに尾崎翠の世界そのものではないだろうか。例えば「木犀」のN氏と「チャアリィ」と、ポテトあるいはN氏の牛の関係。例えば「途上にて」の中世紀氏と「ナヂモヴァ夫人」と、きんつばの関係。「花束」のこんな読み方があったのだ。 この本で、尾崎翠は野溝七生子と深尾須磨子の間に挟まれている。野溝七生子は「ドッペルゲンガー」の文脈で分析されているが、翠の読者は即座に「こほろぎ嬢」を思い浮かべるだろう。「しゃあぷの魂」と「どっぺるげんげる」だ。深尾須磨子は、雑誌『詩神』の座談会で翠と同席しているが(映画『第七官界彷徨・尾崎翠を探して』では二人の対談に改変)前記岩波のセミナーでは、西洋の先端的な性科学を学んだ両性愛者、つまりバイ・セクシュアルとお聞きした。ハブロック・エリスの変態研究なども移入された「時代の空気」が伝わってくるようだ。 深尾須磨子の後は、林芙美子だが、翠との深い関わりについては「01・8・31」の編集後記で紹介した芙美子の日記をご覧下さい。今回の『読む女 書く女』は、作家一人につき見開き2ページの短いエッセイだが、読んでいくと根っこが複雑微妙に絡み合った、球形の巨大な幻想植物園のよう。個人的にもっとも興味を惹かれたのは、尾崎翠が鳥取に逼塞したのとは正反対に、同時期、海外の植民地に渡って文章を書いた(今ではほとんど忘れられている)一群の女性作家たちだ。 ♪ 思いも寄らない出会いというものがある。3月に開かれた「調布映画祭2004」で『第七官界彷徨・尾崎翠を探して』が『百合祭』とともに上映されたが、その際に浜野監督に渡された一本の論文があった。現役の精神科医である渡辺由紀子さんが、1999年に『横浜医学』(横浜市立大学医学部)第50号に発表した「尾崎翠の病跡」の抜き刷りである。 この論文では病跡学(Pathography)の立場から,尾崎翠の生活史、創造へのモチーフ、風土、フロイトの著作との出会い、恋愛体験、作品に見られる幻覚症状、第七官界の成り立ち、などが分析される。なかでもわたしが教えられるところの多かったのは、ミグレニンの乱用が引き起こす幻覚症状と、内因性の精神の病いの関係について、専門医の見地から語られていることだ。ミグレニンが今でも薬局で入手可能というのには驚いたが、翠の場合、大量のミグレニンによって生じた幻覚を、第七官界として作品化した、というような単純な事態ではない、と渡辺さんは指摘する。 「翠は単に創作に利用するためだけに大量のミグレニンを用いて意識的に幻覚を呼び込んだのではなく、むしろ創造過程における膨大な心的エネルギーの結集である『飛び越え』に猛進する自我を崩壊-解体から阻む安全装置として利用を試みたのではないか。作家は『強度の高い創造性は主体解体性、つまりは狂気の危険性をより多く含んでいる』ことを知っている」 「(大量のミグレニンによって引き出された第七官界では)作家を含めたどこか日常から外れた人々の内的緊張が解放され、実存的な不安が覆い隠されるために危うい自我も守られるのである。すなわち、翠にとって大量のミグレニンは、第七官界の創造という点において生の戦略のひとつであり、その目論見はある意味で成功したのである。日常の臨床において、幻覚が人格の解体を防ぐ役割を果たすことがあること、とりわけ、主体を言語の世界につなぎ止めておく効果を持つ言語性の幻覚のポジティブな役割については、つとに知られるところである」 ミグレニンは二重の役割を果たしていた。しかし、そうした意図を超えて、幻覚が主体を支配するプロセスがやってくる。このほか、翠が執着した円環構造とユングのマンダラとの関係、冒頭から削除された「模倣」という言葉と、精神医学における「ふり」「ふるまいかた」の関係など、わたしには啓発される指摘が多かった。冒頭の要旨で「臨床的には基底にある分裂病圏の病に薬物中毒が絡み合った病像を呈し、作品表現にも病理性が顕在化しているが、渾身の力を込めて築き上げたその感覚世界は人々の心を深く魅了する。同時に、病を基底として成り立っているものに対する我々精神科医の目を啓かせてくれるのである」と書いた渡辺さんは、結びでも次のように記す。 「ミグレニンなくしては翠の第七官界は存在しえなかったという仮定も成り立つが、たとえそうであってもこの作家の創造性が損なわれるものではない。大いなる創造とはいつの場合もこのような生死をかけた限界状況のなかで、あるときは病との共生、もしくは病を基底として生まれるものだからである。そしてこの事実は、遥かなる時を越えてこのような天才の創造的所産を享受している我々に、精神科医の前には『病者』としてしか立ち現れることのない『非正常者』の健康な生のいとなみについて改めて考えさせてくれる」 なかなか参照しにくい文献だと思われるので、やや立ち入った(主観的な)紹介をしてしまいましたが「『非正常者』の健康な生のいとなみ」という言葉にわたしは感銘を受けました。尾崎翠を通して多くの人と出会い、そのたびに尾崎翠と何度も出会い直す。冒頭さんざん愚痴った今回の編集後記だが、私たちはきっと幸せな人生を送っているのでしょう。 |
||||||||||
| 04・05・15 ヤマザキ | ||||||||||
|
||||||||||

|
|
『第七官界彷徨 尾崎翠を探して』上映委員会 |