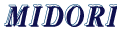
編集後記

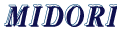 |
編集後記 |
 |
●「朱塗りの文箱」に封じられた謎● |
|
#今年の「尾崎翠フォーラム・in・鳥取」に参加しながら、わたしの頭のどこかで絶えず、微かに鳴り響いていたのは、松下文子さんの遺族から稲垣氏に託された「朱塗りの文箱に大切に収納し秘蔵」されていた、尾崎翠の「未発表作品」への不協和音であった。筑摩書房の定本全集発刊時に喧伝されたもので、映画のシノプシス「瑠璃玉の耳輪」や短編「香りから呼ぶ幻覚」「ある伯林児の話」、「詩『嵐の夜空』」が全集に初収録され、それ以外に「習作数編」も含まれていたという。(定本全集下巻の「解説」より) 今回わたしは、パネルディスカッションのコーディネーターとして、森澤夕子さんの発表に備え、これらの作品を再読した。この「朱塗りの文箱」への疑問は、すでに『鳩よ!』99年11月号の「エルゼ嬢」問題の時に書いたが(本HP「文学」コーナー、および編集後記00年9月27日参照)、今回、該当作品や稲垣氏の同誌に書いた解説を改めて読み直し、そして写真版の生原稿をつくづく眺めるうちに、根底的な疑念にとらわれたのだ。もちろん、稲垣氏をしつこく批判してきたわたしの妄想として読んでもらってもいいが、「朱塗りの文箱」に入っていたのは、本当に翠の作品だけだったのか、松下文子さん自身の作品もあったのではないか、さらに憶測すれば、映画シノプシスは、二人の合作の可能性もあり得たのではないだろうか? #稲垣氏は「松下文子は、彼女の結婚直前のこの尾崎翠との二人だけの共同生活の中で、いわば彼女が翠に書かせたこれらの未発表作品だけを、自分自身の詩作品とは峻別して、朱塗りの文箱に大切に収納し秘蔵した」(定本全集下巻の解説)と、例によって見てきたように書いている。しかし『鳩よ!』の解説では、「翠の作品と決められないもの、翠の作と確認できても完成度がいま一つの習作は、全集収録を見送った」ことなどが記されている。松下さんは、決して翠の「未発表作品だけを峻別」したわけじゃなかったのだ。 もし「翠の作品だけを秘蔵した」のなら、創樹社版の全集編纂前に稲垣氏は生前の松下文子さんに会っているのだから、その際に提供されてしかるべきだったのではないか。死後、遺族から善意で提供されたそれらの原稿に、松下さんがどのような思いを抱いていたか、知る術はない。 もっとも、わたしが一度だけ氏に面会した時には、松下さんを「家政科の女のおせっかい」だとか、また、ここには書きたくない言葉で松下さんの容貌まで含め誹謗中傷していたので、二人の出会いは決して幸せなものではなかったのだろ う。ところが、遺族から「朱塗りの文箱」を託されるやいなや、松下さんに対する筆致が相当柔らかくなっているのは、いかにも打算利得がストレートに反映する氏の文章らしい。 しかし、いったい誰がどういう根拠で、翠の作品と他の人の作品を区別するのか、作品の「完成度」を誰がどういう資格で判定するのか、また「定本全集」に収録しなかった「習作」を、後で雑誌の特集に提供するのは、どういう権利と意図によるものか(翠の原稿料、あるいは雑誌掲載の謝礼は遺族に支払われたのか。翠の生原稿を稲垣氏が私蔵し、そこから発生する著作権を私物化しているなら、法的に問題があると思われる)。 雑誌の解説で「貴重である」とか「後の傑作」「に結晶するモチーフがすでに現れている」と書くぐらいなら、最初から全集に入れろ。そこまで意義付けた作品が、結局、尾崎翠の創作じゃなかったのだから、ほとんどマンガである。この辺のまことに大雑把で恣意的なところが、稲垣氏を相手にする時の悩ましさだ。 #わたしの推論を言ってしまえば、「香りから呼ぶ幻覚」は翠の作品、「エルゼ嬢」は松下文子さんの翻訳草稿、「ある伯林児の話」は松下文子さんの作品、「瑠璃玉の耳輪」は二人の合作、「詩『嵐の夜空』については、分からない。 このうち、根拠がありそうなのは「エルゼ嬢」で、『鳩よ!』に写真版が出たおかげで分かったことだが、明確に「松下文子」の署名があるこの草稿は「翠の字じゃない」という縁者の方の声も聞いた。他の3作品については、文体から受けるわたしの「勘」なので、はなはだ当てにならないが、状況証拠から考えて、尾崎翠が松下文子名義で短編を執筆した、とは考えにくいのだ。 稲垣氏の定本全集解説によれば、「香りから呼ぶ幻覚」と「瑠璃玉の耳輪」の署名は「丘路子」で、他の原稿の「中には松下文子となっているものもある」。そのひとつが「エルゼ嬢」だったわけだが、『鳩よ!』の解説では、他に「松下あや子」という筆名があったことも記している。(小出しにするな、本当にもう!) それでは、それらのいくつもの署名の作品を、氏はいかなる理由で翠のものであると判定したのか。「筆跡、筆致、モチーフはもちろん尾崎翠」(定本全集)、「筆跡も発想も表現も、まちがいなく翠の原稿作品」(『鳩よ!』)。要するに稲垣氏の主観的判断に過ぎず、太鼓判を押した「エルゼ嬢」が、「モチーフも発想も表現も」シュニッツラーだったのだから、わたしの「勘」同様、当てにならないこと、おびただしい。 筆跡に関しては、考証の専門家の鑑定にゆだねるべきだが、定本全集下巻の口絵に載っている、松下文子宛書簡の写真の「文子様」の文字と、『鳩よ!』の「エルゼ嬢」に署名された「文子」の文字を比較対照すると、まず同一人物の手になるとは思われない。そもそも、自身が文筆活動を行った松下文子さんの所蔵していた一群の原稿が、ほとんど翠の作品であると考える方に無理があるのではないか。 #なぜ、尾崎翠が自分の原稿を「松下文子」あるいは「松下あや子」(これはむしろ松下自身さんのペンネームと考えた方が自然だ)といった別名義で書く必要があったのか? 下巻の「解説」で、氏は次のように推測する。「出版社に持ち込んだり、プロダクションに郵送したりしたのは松下文子の意志によるので、不採用の場合のことも慮(おもんばか)って、尾崎翠でない別名を使ったとも考えられる。また、翠の側で、当時は文子と一心同体の共通感覚に燃えた時期でもあり、『これはあなたのものよ』とあえて文子の名を記した場合もあり得る。松下文子名義は、翠と文子双方の友情または愛の証と見ることもできよう」。 ここで氏が、いくつかの根拠らしきものを「考えられる」「あり得る」「見ることもできよう」と次々重ねているのは、ひとつとして決定的な理由が見当たらないためだ。なかでも、最後の「愛の証」など、氏が本気で書いているのかどうか、眉唾ものである。 原稿の持ち込みや郵送が松下文子担当だったことが、どうして別名を使うことにつながるのか? この文脈では「不採用の場合のことも慮っ」たのは松下さんということになるが、「エルゼ嬢」などは、草稿の書き出しからすでに署名とタイトルが入っている。原稿を送る段階で署名が添付されているなら、松下さんの配慮ということもあり得るかもしれないが、尾崎翠が自分の作品を、よりによって詩人としてすでに作品を発表している親友の名前で、書き始めることはあり得ないと、わたしは思う。 #これらの作品はたまたま不採用だったかもしれないが、もし出版社で採用された場合のことを考えると(最初から採用されないことを前提に、作品を書くはずはない)、当然松下文子名義で、尾崎翠の作品が掲載されることになる。しかし果たして二人は、そんな事態を当たり前のこととして受け入れただろうか。文子の側から考えても、了解できる話ではない。「売り込みや懸賞応募を」しない翠に代わって「出版社に持ち込んだり、プロダクションに郵送した」というが、その当の作品が松下文子名義では、単に自分の売り込みに行っただけの話になるではないか。そんなバカなことがあり得ようはずはない。 この下巻の解説の別のところでは「松下文子が、昭和初年に翠がいい作品を書きながら、空しく筐底(きょうてい)に秘めたままなので、自分名義や別のペンネームで心当たりの雑誌の編集部に送りつけたり、無理やり新作を書かせたりしていたらしいのも、翠のあまりの引っ込み思案にたまりかねたからであろう」とも書いている。 これまた意味不明の文章なのだが、まず先に翠の書き溜めた作品があって、それを文子が送りつけたなら、「エルゼ嬢」のように書き出しから「松下文子」の署名が入っているはずがない。また「引っ込み思案をたまりかねた」からといって、親友の作品を自分の名前で編集部に送ったりするだろうか。稲垣氏ならやりかねないだろうが、まず無理な想定だ。 このように、稲垣氏の「解説」を仔細にチェックすると、平気で矛盾している箇所がゴロゴロ出てくる。ひとつの文章でさえそうなのだから、以前書いた文章と比較対照すると、後になるほど、明らかに氏の妄想によって捏造されたとしか言いようがないフィクションが混ざり込んでくるのだ。翠を鳥取に連れ帰るとき、長兄が高橋丈雄に与えた下駄のエピソードなど、その典型である。(これについては、すでに映画のパンフに書いたので省略する) #松下文子と、尾崎翠の間に、いくつかのペンネームで書かれた、一群の小説や翻訳、映画のシノプシスが存在する。確実なことは、これだけだ。 松下文子さんが所有していた「松下文子」あるいは「松下あや子」と署名された原稿は、まず本人のものと考えるのが順当だろう。「丘路子」と署名された2編のうち、シノプシス「瑠璃玉の耳輪」は本業外なので、ペンネームを使う必然性があり、尾崎翠作品である可能性は高い。ただわたしには、すべてが翠のものとするには違和感が残り、確かに「山崎」の幻想などは翠の感覚そのものだと思うが、そこだけ妙に浮き上がっている。シナリオを複数のライターが共同で書くのはよくあることで、二人の合作の可能性はないだろうか。 もうひとつ「丘路子」名義だとされる「香りから呼ぶ幻想」は、くっきり翠の刻印が押された作品だと思われるが、どうしてペンネームになったのか? 「詩『嵐の夜空』」は、わたしにはよく分からない。類推も控える。 「ある伯林児の話」については、この文体が翠のものだとは到底思えない。実際にベルリンに滞在した松下文子の作であるとするほうが素直だが、署名は何だったのだろう。稲垣氏は「エルゼ嬢」について、文子がベルリンから送ってきた「ワイマール時代の雰囲気の残る新聞、週刊誌の短編やエッセイにヒントを得て、触発されて書いたものだろうか」などと強弁し、墓穴を掘ったが、この作品もその系列に入る。何が何でも尾崎翠を祭り上げるために、空しい粉飾を重ねることはやめた方がいい。 #いずれにしても、これらの「生原稿」が、今、どこに、どんな形で保管されているのか気にかかる。稲垣氏が私蔵しているのだろうが、その現物を専門家の手で考証しない限り、いつまでたっても、何を言っても、類推に過ぎない。当初、1巻本として企画された筑摩書房の定本全集が、直前になってこれらの原稿が発見され、急遽2巻本になった経緯があった。おそらく複数の目でじっくりと考証されたはずがない。 最初の創樹社版全集における氏の功績は認めるが、複数の協力者があってのことだった。いまや虚実ないまぜの評伝作者に過ぎない稲垣氏を「一人権威」として奉った筑摩書房版の定本全集は、功罪相半ばし、わたしたち読者は批判的に読解することを要求される。しかし、信頼すべき「解説者」の不在は、読者一人一人が翠の言葉と直接向かい合うことになり、案外喜ぶべき事態かもしれない。 #目下「台湾国際女性映画祭」に参加し、台北に滞在している。メールで送稿し、インターネット上で校正する、そんな時代なのだ。しかし、これも高尾事務所の鈴木裕子さんの手腕があってのことであり、わたしのなかなか終わらない追悼文の意を汲んで、すっきり見事にデザインしてくれたことに、今更ながら感謝したい。 この映画祭では、『百合祭』と同時に『第七官界彷徨・尾崎翠を探して』も2回上映された。一助と二助が障子越しに、蘚の進化論などを議論するシーンや、皆が片恋の歌を合唱し、二助が自室で「こんな晩に片恋の歌を歌う奴があるか」とボヤくシーン、さらには雨の夜に2軒の家の間を風呂敷包みが往復するシーンなどで、若い観客の大爆笑が起こった。尾崎翠の感覚は、決して多数派ではないが、時代を越えてインターナショナルであることを、改めて認識した。 |
| 02・09・17 ヤマザキ |

|
|
『第七官界彷徨 尾崎翠を探して』上映委員会 |