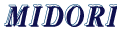
編集後記

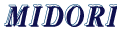 |
編集後記 |
 |
●これは編集後記か? 知友の翠探究に大いに啓発され● |
|
# 近藤裕子さん(現・札幌大学助教授)に誘われ、参加した「女性文学会」でお会いした風日舎の吉村千穎氏が、浜野佐知監督に新刊『林芙美子・巴里の恋-巴里の小遣ひ帳 1932年の日記 夫への手紙』(今川英子編。中央公論新社刊)を送ってくれた。氏が編集協力として名をつらねるこの本の、1932年の日記に、尾崎翠に触れた箇所があるためだが、帰郷直前の精神の錯乱や、高橋丈雄との「恋愛問題」を記して生々しい。 「七月十一日(月曜日)(中略)かへりひとり尾崎女史宅により。アイスクリームモナカ持参す。仕事中にて、ゐづれを見ても辛らそうだ」 「七月三十日(土曜日)報知新聞を朝中井駅まで買ひに行く、尾崎女史に会ふ。モンツキの老人と歩いてゐた。后前中に速達で報知原稿送る。夕方尾崎女史に呼ばれてあはてゝ行く。まるでトテツもない神軽(経)衰弱らしい。何か追はれてゐるやうだと云ふし、文壇的に行きづまった風な話をしてゐる。お互ひに感じる事だ。十時頃まで話してかへる(後略)」 「七月三十一日(日曜日)昼から尾崎女史宅に行くが来客にてあがらず、夕方尾崎女史のかへりだと云って、高橋(丈雄)和田(十和田操)の二君来る。尾崎女史の発狂に近い神軽(経)衰弱を心配す、「旅にも行かぬ」と云ってゐたそうであった。さからっても仕方がない。夜、水瓜なぞ破ってたべるが、うまくなし。終夜、尾崎女史の発狂について眠れず、仕方がない。夜更け、高橋君とこへ泊ると云って、尾崎女史高橋君あいさつに来る。女史いそいそとしてゐた。病気がなほってられますやうに。緑(芙美子の夫、手塚緑敏)は独身でゐると医学上から云って、性的ヒステリーだと云ってゐた。」 この後、芙美子は8月2日から信州への旅に出る。その旅先でのこと。 「八月三日(水曜日)(前略)尾崎女史高橋君と結婚すとたよりあり、さてもめでたき事かや。」 八月十二日に帰京する。 「八月十六日(火曜日)(前略)朝湯にはいって少しばかり眠ろうとしたところに和田君来る。尾崎女史の話をする。全く、尾崎女史の問題には疲れてしまう。二人で尾崎女史宅に行き、四五時間も、高橋君との問題について話すが、しばしば突評(拍)子な唄が出て、力むでゐる仲人役の私達のシンタンを寒からしめるものがある。夜、高橋君来たりて、また尾崎女史宅に至りかへり夜中の一時一寸前、テットウテツビ、尾崎女史にくれる。(後略)」 「八月十七日(水曜日)何もかけずヒカンする。朝高橋君来訪、やっぱり尾崎女史と結婚すると云ふ事であった。(中略)かへると、又尾崎女史の階下の人達がなきこんで来た。自分まで気が狂ひそうになって来る。尾崎女史宅よりミグレニンをとって来る。あんまり飲まさない方がいゝ。林芙美子よ! も少し大りょうで偉くなれ! 就寝夜中二時。」 「八月十八日(木曜日)夜中より雨、昨夜遅かったので朝寝した。高橋君来訪、早く、こんな問題からかたづきたいものだ。(後略)」 この後、林芙美子は仕事や新居に奮闘し、尾崎翠についての記述はない。これを、高橋丈雄が創樹社版の月報に書いた「恋びとなるもの」と突き合わせると、7月31日が、高橋と十和田が尾崎翠の葉書を受け取って駆け付けた日ではないだろうか。高橋は「昭和七年八月酷暑の頃」と書いているが、翌八月一日から疾風怒濤の日々が始まる。31日の夜更けに「高橋君とこへ泊ると云って、尾崎女史高橋君あいさつに来る。」というのは、おそらく高橋の大岡山の一軒家に向かったのだと思われる。 芙美子が信州から帰って来ると、修羅場が展開していたわけだが、長兄はいつ上京し、翠を鳥取に連れ帰ったのか? 高橋は、翠の長兄に下駄を買ってもらい「思えば、僕は、その十日あまりを、彼女のことのみに気を奪われて、なりふりなど眼にはいらず、手渡されてみれば、敝履のごとくちびくれた履きものを突っかけて炎天下を彷徨していたのであった」と書いている。 芙美子が最後に日記で触れた8月18日まで、すでに20日近く経っているが、この後も騒動が延々と続いたとは思わない。当て推量だが、芙美子が「早く、こんな問題からかたづきたいものだ。」と書いているのは、あるいは長兄の上京のニュースを踏まえているのではないか。いずれにしても、翠と長兄が鳥取に帰って行ったのは、1932年(昭和7年)8月20日前後だったはずだ。 全集の年譜では「9月上旬」となっているが、実際には上記のようであったと思われる。 # 錯乱する翠は哀しいが、鳥取のフォーラムを前に、石原深予さん(大阪大学大学院文学研究科国文学専攻博士前期課程修了)が岩井温泉の翠資料館で公開した新資料の一つに、翠の日常の素顔を伝えるコラムがある。樺山千代による交友記で、『文学党員』昭和6年4月号に掲載された。 樺山千代は、親しい文学仲間で、年齢的に妹分のようだが、 「(前略)たとへば女史が銭湯で、私の洗髪を手伝ひ、體の冷えた頃に背中から熱いお湯を浴びせてくれたところで、それは私にとっては、もはや、太陽の存在のやうに、あたりまへになった有難さであって、恐縮したり禮を云ったりする事の方がかへって不自然である。全く至れりつくせりの親切者である。」 これに対する千代のお返しは「女史の網野菊のやうに頸すぢに垂れ下がった頭髪」を刈ってあげる事だったとか。 「女史の創作に一點のすきのないやうに、女史は裁縫をしても料理をしても常に綿密である。誠あり、血あり、涙あり、そのくせ、末梢神経的な五月蝿さはないし、こんな人を女房に持ったらいゝなアと、私は時々、男でなかった事を後悔する。(後略)」 「女史は徹頭徹尾正直者である。そのため私といふ嘘でもちょっと撫でられてゐたいやうな甘い人間は、時にまごついたり腹を立てたりして、上出来のカクテルの表面に泡を立てる。が、正しい感覚を取り戻した時には、いつも女史の正直さと、根本的な親切に頭を下げ感謝する。」 「カクテルの泡」というのは、二人の交友を「出来のいゝカクテル」になぞらえているからだが、千代が「泡を爆発」させ、怒りにまかせて帰った後のこと。 千代「憤然と帰って来たけれど、實は私が悪いんだから私は悔んだ。それにちっとも来てくれないし…」 翠 「私も何故、明日行くと一言云はなかったらうと思ってそれが悔いられた。しかし根本は分かって るのだし、ぐらつく筈はないんだから、その點の安心はあった」 「爆発」の後、二人は再び会って、男性作家の家を訪ね、留守宅に上がり込む。 「盗んで行きたいものもないわね」 「蓄音機かこの豆煙管くらいのものかな」 「いやにハイカラな椅子があるじゃない?」 「どこからかっぱらって来たのかな?」 おそらく、煙草を吸う翠が後側と思われるが、悪戯好きな女子学生のような会話だ。独身者同士の腹蔵のなさがうかがわれる。この時の事を思い出して、千代が言う。 千代「だけどあの時はほんとにうれしかった」 翠 「お互い様」 千代「だけどお互い爆発につひては一寸もふれないでケロリとしてたじゃない?」 翠 「ちょっと、テレたのさ」 二人の会話を通して、口数は多くないが、実にさっぱりした気性の、大らかで温かな、翠の人柄が伝わってくる。 # これらの新資料を発掘し、実証派のように見えた石原深予さんだが、修士論文を拝読して、吃驚。晦渋な文体の神秘派のようではありませんか。タイトルは「尾崎翠『地下室アントンの一夜』論」。あまり論じられることの多くない作品だが、翠が鳥取に帰る前に、最後に中央の雑誌に発表した小説。帰郷後、誌や短いエッセイは書いたが、小説はない。つまり、これが最後の小説ということになる。 登場人物が「歩行」と重複するので、その続編、あるいは「歩行」の創作ノート(by 稲垣真美)といった見方をされてきたが、石原論文は「多作品との関連にとらわれることなく、独立したひとつの作品として、解釈し、論じる」ところからスタートする。 稲垣氏をあまりバカにできないのは、わたしもまた何となく続編のつもりで読んでいたからだが、小野町子のように「第七官界彷徨」から引き続き登場してくるキャラクターも含め、先行作品と一切切り離した時に、何が見えて来るか? この作品は、(幸田当八各地遍歴のノオトより)(土田九作詩稿「天上、地上、地下について」より)(動物学者松木氏用、当用日記より)(地下室にて)というパートに分かれている。最初の幸田当八ノオトなどは1行だけだが、メインは「九作詩稿」。石原さんは、そこで「語られる松木は『僕』が思いえがいた松木であり、『僕』が創り出した仮象としての人物である」「松木は実体のない仮想敵である」という大胆不敵な断定を、早々と行う。松木氏は存在しない? それでは、松木氏の日記とは何か。 「『松木日記』は『日記』であるにも関わらず、日記の語り手『余』は日記内で『余は思い切って出かけてみることにしよう。/ようやく土田九作の住ゐに着いた。』というように、空間を移動する。この日記を書いているのが本当に『実証派』である『余』なら、このような逸脱はあり得ないだろう」。なるほど! 改めて「地下室アントン」を読んでみると、「歩行」とは著しく異なって、敵役の松木氏が実証派に徹していない。キャラクターが、九作と相互乗り入れしているように見える。これをわたしは、従来、冒頭の幸田当八ノオトに記された「求反性分裂心理」による、対立者同士の内的な相同性、と解釈していたが、これでは確かに日記中での、実況中継のような空間移動は説明できない。 松木氏のみならず、幸田当八、小野町子、松木夫人、ことごとく「土田九作一人の内的な要請により、彼の心中で創出され想像された人物たちである」、つまり九作以外はすべて「仮象」であるという石原さんの説に従えば、最後の蜃気楼のような朦朧とした「地下室」は、九作の心の中の部屋であるということが、明快に諒解できる。 それでは、「地下室」の語り手であるところの「私たち」とは誰か? 石原さんは「『一人の詩人』の『限りなく広い』『心』に点在している、『私』の総体ではないかと考える」。すなわち「こほろぎ嬢」の語り手でもあるところの「私たち」。 石原論文は、この登場人物たちの実在仮象をめぐる問題系と、もうひとつ「耳鳴り」をめぐって、聴覚の異常と、それからの回復を願う問題系が絡み合って進行するのだが、九作が「おたまじゃくし」に深く捕われて、離れることができないのは「おたまじゃくし=音符」であり、失われた聴覚の代わりに代替物として視覚化されたものだから、という指摘は、一見思いつきのようで、実は尾崎翠の狙いを見事に射ているのではないか。 だからこそ、地下室の扉は「キューンと開いて、それは非常に軽く、爽やかに響く音」をさせ、聴覚の異常(=生命体としての危機)を回復させる場所として期待される。まして、そこは医者であった「アントン・チェホフ」の名を冠せられ、「心理医者」である幸田当八が存在し「治療」もまた大いに期待できるのだ。では、九作は、この爽やかな地下室において治癒したのか? 当八は言う。「君は今夜住ゐに帰って、ふたたび詩人になれると思はないか」 九作は、明るく答える。「さっきから思ってゐる。心理医者と一夜を送ると、やはり、僕の心臓はほぐれてしまった」 明るい展望の内に終わりそうなところだが、当八の言葉は思いがけないものだった。 「さうとは限らないね。此所は地下室アントン。その爽やかな一夜なんだ」 爽やかなのは、この一夜だけで、「住ゐ」に帰ったら、元の木阿弥だと言ってるのである。読者がポーンと放り出されるところだが、石原さんは地下室に町子が現れない以上、「地下室アントン」は「完全な治療を施してくれる場所ではなくて、対処的治療、応急手当を施す場所であった」と解読する。最後のセリフの意味は 「幸田当八として形象されている根底的な判断を下す何者かからの『お前は治っていない』というメッセージの提示であり、また同時に『わたし自身は治っていない』という九作自身の自覚でもあるのだろう」 かっこいい! わたしは石原論文とともに「地下室アントンの一夜」を読み返すことで、はじめてこの作品の持つ確かな手触りを実感した。論旨および文体は、どこか狭く暗い洞窟をくぐって進むような趣があるのだが、この末尾近くに至って論文読者もまた開放される(「解放」じゃなくて)。「治療」なんてあるもんか。これで、いいのだ。 これを最後の小説として遺した翠の人生を重ねると、作者自身も「地下室」へ降りて行く覚悟でこの作品を書き、また実際、「地上のすべてを忘れて其処へ降りて」行ったように思えるのだが、さすがに石原深予さんは学究の徒、人生と作品をチャンポンにすることには禁欲している。稲垣老も少しは見習え。 # 「蜜柑の発育による三五郎の恋情の変化」。何やら、「第七官界彷徨」に出てくる論文のタイトルのようだが、神戸松蔭女子学院大学文学部国文科の押切那岐佐さんの卒業論文に出てくる項目名です。昨年11月に岡山市で開かれた「地域映像祭」で、神戸からやってきた大学生の押切さんとお会いしました。今年卒業するという彼女に、卒論ができたら読ませてほしいとお願いしたところ、春先に送って頂いたのですが、これがとても新鮮なアプローチなので、ご紹介したい。 「『第七官界彷徨』町子の居場所を探して-時代とともに生きる作家 尾崎翠-」と題されたこの卒論は、「1 時代背景とその文体が語るもの」「2 物と人間の関係について」「3 においと、ものの本質について」「4 映像からみる第七官界」(何と、わたしたちの映画について1章さかれている)「補論 尾崎翠と吉本バナナについて」という構成になっている。 第1章の視覚的文体について、リヴィア・モネ教授や群ようこが引用されるなど、若い世代の関心の方向性が示されるが、わたしがもっとも膝を叩いたのは、第2章の物と人間の関係の考察に際し、押切さんが「物の配列地図」を作ったというところ。これはもちろん、翠自身が「『第七官界彷徨』の構図その他」で「場面ごとの配列地図のようなものを制作した」と書いていることに由来するが、物を中心に配列地図を再現すると「いくつかの謎と疑問、発見が見えてきた」。 まず「最もわかりやすく物の影響を受けているのは三五郎である」。町子が上京してきた時、発育がひどく遅れているように見えた生け垣の蜜柑だが、酸っぱいながらも食べられるようになると、蘚の花粉のプッシュもあって町子の首筋に接吻する。「垣根の蜜柑もいくらかうまくなったよ。おやすみ」と言いながら。次に、それが色付きはじめ、美味しそうになると、三五郎は隣人の女子学生と夜間、一緒にひとつの蜜柑を分け合って食べる習慣を持つ。しかし、間もなく蜜柑は家主の老人によって、ひとつ残らず収穫され、隣人もまた、あっさり引っ越してしまった。 「蜜柑の成長が描かれる後には、必ず三五郎が恋愛感情に基づき行動する場面が描かれていることが分かる。蜜柑が実を結ぶと三五郎の恋愛も実り、収穫と同時に三五郎の恋愛も終わる」。確かに蜜柑が姿を消すと、三五郎もフェードアウトし、街角で「銭湯に行く姿で夜店のバナナをながめて」いるのを、使いに出た町子に目撃されるのを最後に、もう登場しない。賑やかなお調子者としては、侘びしい限りだ。 同じことは、蘚や二十日大根の生育と、二助の心理状態についても言えると、押切さんは指摘するが、わたしが興味を惹かれたのは、町子と「首巻き」の関係について言及しているところ。まず「くびまきにまつわる人物は町子の心を許した相手、町子の心を占めている人物である」。最初に、もちろんお祖母さん、次に三五郎。彼は町子の髪を切って、頸をあらわにする。「この頸というものが尾崎翠の作品の中では、しばしば性の象徴として描かれている」が、三五郎に接吻された町子は、翌日からボヘミアンネクタイで頸を隠してしまう。「町子はあくまで女の子という存在であり、大人になることを拒否したのである」。 その町子が、ネクタイを外すのは、隣人の女子学生が現れてから。これを押切さんは「町子の関心が三五郎から隣人に移ったことを示している」。この辺り、全く拍手喝采したくなるような展開で、わたしは嬉しくなる。「ここで注目すべき点は隣人が女性であるということだ。隣人は同性である。つまり町子は頸を隠す必要がないのである」と、押切さんが、比較的あっさり片付けているのが、少々残念。隣人の女子学生との関係には、異性愛の枠組み、あるいは男女が一対となる対幻想を越えて行く可能性(石原深予論文で触れられていた「トライアングル」な関係もそうだが)を見たい、わたしとしては。(個人的、個別的、一般性のない関心かも知れない) 次に、ネクタイが登場するのは、失意の同族である一助に「肱蒲団」を作る場面。一助に対して、頸を隠さないのは、兄であり、失恋者であるからだ。そして、さて、ラストに至って、町子は柳浩六にくびまきを買ってもらうが、これを押切さんは、異性の彼に惹かれる一方で、やはり頸を隠そうとしている、と読む。しかし、浩六は遠くへ引っ越してしまい、不用になったくびまきは「ボヘミアンネクタイが、かつてかかっていた場所へかけられる」。可哀想な三五郎。 この後、押切さんは、物と匂いを手がかりに第七官界の探究に向かうが、これについては従来も、今後も、諸説紛々あり、正解は存在しない。だからこそ第七官界なのだ。その探究の前提として押切さんが採用した「物の配列地図」からの読解に、わたしは目を見張った。卒論で、このようなレベルの論文が現れることは、まことに心強い限りである。 # 「尾崎翠フォーラム・in・鳥取」で、鳥取入りしたわたしたちを出迎えたのは、重戦車のごとき圧倒的なボリュームの土井淑平(どい・よしひら)論文であった。「ユーモアの精神とパロディの論理-尾崎翠と花田清輝を結ぶもの」と題された、優に一冊の書物ぐらいの分量はある、この論文は、現代哲学や文化芸術に関する今日的な理論を博引旁証するだけでなく、アリストテレスに発する笑いや悲劇の定義を辿り、さらには「模倣」やレトリックの原義をめぐってギリシャ語に遡るなど、まさに天馬、空を行く勢い。いったい旅先で、辞書もナシにこれを読めというのか! というのは、わたしの場合、嘘で、実はフォーラムに関する日本海新聞の原稿を書くために、事前にコピーを送ってもらっていたのだが、もちろん辞書や事典類を引きながら読んだ。尾崎&花田ファンの一人としては、大いに楽しめるが、しかし動員される理論や用語の多彩さは、例のリヴィア・モネ教授の長大な論文の向こうを張るもので、フォーラムを飾るに相応しい大型評論と言える。 モネ教授には、鹿爪らしく、どこか理屈を見せびらかすようなところを多少感じたが(その代わり、断定がスマート!)土井さんの場合、壮大な理論の仕立てを解きほぐして行くと、ご自身が面白がって、ニコニコしながら書いているのが見えてくるようだ。中でもわたしが、ほとほと感服したのは、アリストテレスの「悲劇とは行動の模倣である」という有名な定義を、花田が「悲劇とは擬態である」と再解釈し、さらに「喜劇とは擬態である」とひっくり返したのを受けて、そこからジョゼフ・W・ミーカーの『生存の喜劇』(邦題『喜劇とエコロジー』)へと繋いでいるところだ。 「自ら生き延びるために、環境が与える機会を利用したり逆手をとってやりくり算段する『喜劇的生活様式』は、すべての生物にあまねく見られるものであって、しかも生物進化という現象自体が環境への適応と調整の過程で、『行き当たりばったりになんとか切り抜けていく』のを建て前とした『破廉恥で不節操な日和見的な喜劇』なのだ」 ミーカーという人は「生物学者にして比較文学者」だというのだが、「パストラル(牧歌詩)の伝統の対極にピカレスク(悪漢小説)の政治哲学を置き、自由で機敏な行動によって運命の逆手を取りつつ、巧みに環境に適応していくピカロ(悪漢)の生き方を評価する」と聞くと、あら、これ、モロ花田じゃない! エコロジーの著作家にして、運動家である土井さん自らが「喜劇的精神とエコロジー」は密接な相関関係にある、と宣揚するのは、これこそ目からウロコ。決して環境運動は、まなじりを決し、青ざめた正義の御旗を掲げたストイシズムにのみ導かれるものではないのだ。これがまた「対立物を対立のまま統一する」という花田テーゼや、花田言うところの「ガルゲンフモール」(絞首台の諧謔。ギロチンを前にしたジョーク)へと、再び返って行くのを目撃するのは、花田ファンとしては快感以外の何ものでもない。 そして、町子や一助、二助、三五郎の住むあの「古ぼけた平屋」「厄介な家」(by 三五郎)こそ「喜劇的精神とエコロジー」を具現化したものだと言うのだ。 「小さく限られた書割りのような一軒の廃屋を舞台に、人、蘚、こやしといった動物・植物・鉱物がそれぞれ変な家庭の一員として共生し、お互い活発に恋愛や研究や議論に励みつつ、不思議な国のアリスさながら、深刻にして滑稽なるドラマを繰り広げるこの『第七官界彷徨』ほど、先に取り上げた喜劇とエコロジーの密接な相関を象徴するものはあるまい」 アリストテレスから始まって、ここに着地するまでの見事な論理展開は、気持ちいい上、美しく、ためになる。他にも「パロディの論理が弁証法の対極にあること」など、有益な指摘は多く、わたしは大いに勉強させてもらったが、親しき仲にも議論あり、で、いささか疑問、というか、質問を呈するなら、これはかなり変則的な花田清輝論なのではないだろうか? 理論装置が花田には見事に適合し、自動的に動き始めるのだが、尾崎翠のミクロな世界には、少し装置がデカ過ぎるような気がしてならないのだ。 あるいは、批評(花田)と小説(尾崎)の違いかも知れないが、尾崎翠のバックボーンの分析や、置かれたコンテクストに関しては全く異論がないものの、小説のディテールをこの徹底した汎パロディ理論で論証していくとなると、どこか、もどかしさが残る。傑作も駄作も秀作も、一切がインターテキストであり、パロディであるなら、尾崎翠の流儀はいかなる手触りのテキスト、パロディを実現し、どこが他の流儀と異なるのか? まあ、しかし、これは重戦車に、小回りのきく戦法を要求するようなものだろう。あらゆる理論に万能は有り得ず、無い物ねだりに相違ない。わたしたちは、土井さんの展開するスペクタクルを充分に堪能した上で、自分のグラウンドに戻り、再度アタックしていけばいいのだ。 # 最後にひとつオマケのように。以前、鳥取県立図書館で「歩行」初出の『家庭』を閲覧しました(1931年9月発行。第1巻第4号)。その際、目にした、挿し絵の脇に付された無署名コメント。 「この短篇の作者尾崎翠さんは日本女子大學を中途退學し、その後文藝に精進して、よほど以前「新潮」に處女作を発表、爾来遅筆で寡作。とくに文壇的に認められていゝ方ですが、惜しいと思ひます。」 「第七官界彷徨」を発表した直後だったが、まだこの程度の受け止められ方だったのですね。知る人ぞ知る実力派、といったところか。同号は「オール女性執筆号」で、編集後記には、編集発行人の中川敏夫が次のように触れている。 「尾崎翠さんも新進です。こんな本格的作家が「かくれている」ことは凡そうそ(嘘)です。私はこの人の前途を見まもってゐたいと思ひます。」 尾崎翠には関係ないが、同じく編集後記で、おそらく女性の編集者3名の連名で、次のように意気が上がっているのが可笑しい。 「オール女性執筆號、萬歳! この一冊を手にして、ある心強さを感じない女性があったとしたら、その人はキッと低能です。」 |
| (山崎邦紀。2001・08・23) |

|
|
『第七官界彷徨 尾崎翠を探して』上映委員会 |