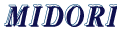
編集後記

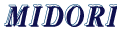 |
編集後記 |
 |
●長々とした編集後記● |
|
# わたしの友人のなかに、塩山芳明という悪役気取りのエロ漫画編集者がいて、98年秋に完成したこの映画を、浜野監督やわたしがいまだに上映やらディスカッションやらで持って回っていることを「一本の映画でいつまで食ってるんだ」などと揶揄するが、「食っている」というのは不正確な表現であって、浜野監督の口癖である「この映画ほどお金にならない映画はないが、その代わり、この映画ほど人に会わせてくれる映画はない」というのが、正直なところである。確かに、通常の進行から言えば「ロードショー→各地の映画館で上映→ビデオ化→TV放映」で1サイクル巡るのだが、プロデューサーを兼ねる浜野監督の執念によって、国内外の映画祭と個別上映会だけで、ここまでやってきた上、ほとんど監督やわたしが出向いて尾崎翠や、この映画の成り立ちについてディスカッションしてきた。これは、当然のことながら、受け入れてくれる上映主体があってのことであり、尾崎翠の生涯と作品に取り組んだわたしたちの思いとは別に、「尾崎翠」を主題化する今日性というものが存在するのだろう。
# 今になって、上映委員会のHPというのも、時機的にはずいぶん間の抜けた所行のような気がしないでもないが、しかし製作・上映の過程で実に多くの方々に出会い、それらは単にパーソナルな交友関係というよりは、「尾崎翠という主題」を巡って関わり合った。これを単に年賀状のやり取りのレベルに終熄するのではなく、主題を深化しながら形として表わしていく上で、今回のデジタル化という方法論ほど格好なメディアはない(のではないだろうか。わたしは初心者で、エラソウなことを言える立場ではない)。思えば「インパーソナル」は、尾崎翠を一貫して評価した花田清輝のスローガンのひとつであった。花田存命なら、インターネットをどう評するか考えることは、楽しい。 # わたしのもっとも好きな花田の著書に『冒険と日和見』(創樹社刊)があるが、これを編集した玉井五一編集長が、尾崎翠の最初の全集を刊行したことは、たとえいくつかの偶然があったにしろ、わたしからすれば必然の糸で結ばれている。映画の企画段階から玉井氏にお会いでき、花田の愉快なエピソードをお聞きできたことは、僥倖(あるいは役得)としか言いようがないが、ここで、エピソードのひとつを披露しておくと『冒険と日和見』のタイトルについて、花田と玉井氏がカツを食いながら相談した。そこで花田が出したのが『月のもの』という案で、玉井氏もすっかりそれに乗ったのだが、翌日先生から電話があり、夫人が「いくら何でも」と言っているので変更したいとのこと。それで結局『冒険と日和見』という表題になったというのだが、夫人の感想が原因であったかどうかはともかく、『月のもの』とは、さすが『恥部の思想』(講談社)の著者である。なお、玉井氏は個人誌として「花田清輝通信」を出すプランがあるそうで、大いに期待して待ちたい。 # いまどき花田について語り合える知友は少ないのだが(前記の悪党、塩山もその一人で、生意気にも『嫌われ者の記』『現代エロ漫画』ーいずれも一水社刊ーという奇書の著者でもある)鳥取での最初の記者会見で初めてお会いして以来、鳥取を訪れるたびに倦まずたゆまず(?)問答を重ねているのが、共同通信の記者にして、エコロジーを主軸とした著書を持つ、土井淑平氏である。語り合うというよりは「花田も吉本も両方読んでいる」ことを自負し、今や吉本の苛烈な批判者でもある土井氏にわたしが質問し、貴重な教示を受けるのが常なのだが(惜しむらくは、楽しさのあまり、酔っ払ってその教えを忘れることが多い)信じられないことに、尾崎翠の幼時に、岩井温泉から鳥取市内に一家が引っ越してきた先が、土井氏の「ひい祖父(じい)さんの代の」別邸だというのだ。現在は畑になっているその土地を、鳥取文学研究者の竹内道夫氏が案内してくれたことがあるが、土井氏には創樹社版の全集が出た翌年の80年に、赴任先の九州のタウン誌に執筆した「美神の仮面ー尾崎翠頌」というエッセイがあり、尾崎翠の姉妹と面識のあった「明治生まれの親父」の回想も記されている。この卓抜な尾崎翠論は、稲垣氏流の悲愴な見方がもっぱらの頃に、尾崎翠の「あたしの顔って、ベエトーベンのデスマスクにそっくりだって友だちに云われるのよ」という言葉(創樹社版全集月報の高橋丈雄の回想)と、黒鉄ヒロシのマンガ「ベートーベン」を結びつけ、花田言うところの「ミューズ」の「お面の裏」に「メランコリーもまたユーモアに転じる、爽やかで明るい、知的な哄笑が隠されている気がしてならない」と喝破しているのは、さすがという他はない。近い機会に、このエッセイは全文掲載したいが、5月に配信された共同通信の記事(資料コーナー参照)は、土井氏の筆によるものである。しかし、一方で人形峠のウラン残土の住民運動に深くコミットしている土井氏が、悠悠閑閑と酒を飲んでいるのを見ると、どうやって時間をひねり出してくるのか、毎度首をかしげざるを得ない。 # マンガといえば、8月に北海道立文学館で上映とトークが行なわれることになったが、これはマンガ家の畑中純氏が、札幌大学の学長室を改造したギャラリーで開かれた宮沢賢治の版画展において、文学館の平原一良氏と出会ったのが、契機となっている。ずいぶん以前に、わたしはマイナーなタウン誌編集者として、デビュー前の痩せて狷介不屈のマンガ家に出会ったのだが、以来、氏が描き続けてきた膨大な作品群を前にしては、口をあんぐり開け、ただ驚嘆するのみ。最近も『ガキ』(太田出版)『愚か者の楽園』(新潮社)という分厚な大著を立て続けに上梓したばかりだが、一方で畑中氏は日本文学にも通暁しており、時代のバックグラウンドも知らないで尾崎翠を語るわたしを見かねて、伊藤整の『文壇史』などを貸してくれる一幕もあった。それを読んだわたしが、どっと冷や汗をかいたことは言うまでもない。昨年、谷崎潤一郎の『鍵』(小池書院)をマンガ化した氏だが、敬愛するつげ義春氏とはまた異なるポジションから、マンガと文学の境界に新たなフィールドを開拓していくことだろう。北海道立文学館の上映の実行委員長を、札幌大学学長で著名な文化人類学者の山口昌男氏が引き受けてくれたということだが、畑中氏の『まんだら屋の良太』をもっとも早い時期に、それもアカデミックな世界から評価してくれたのが、山口先生であった。 # 映画製作の過程で「生涯最悪の二人」(稲垣氏含む)と出喰わしたわたしだが(こういう物言いのシツコサが、わたしが嫌われる所以であることを、ようやく最近になって自覚した)、しかし無数の恵まれた出会いに比べればモノの数ではない。このホームページが成立したのも、かつての専門学校の講師仲間である高尾洋氏(ダメ講師で首になったわたしと違い、強烈なキャラクターで学生に人気があった)との偶然の再会によるものだ。インターネットの概念のレクチャーから始まって、独自ドメインの取得、機能的で見通しのよいデザイン設計、アップと、高尾事務所の高尾氏、鈴木裕子氏、浦野真琴氏の全面的なバックアップを受けた。記して、感謝する。また、高尾事務所のホームページで、佐藤淳一氏が各地の水門の写真(!)をえんえんと展開しているのには、思わず膝を打った。つげ義春氏の『無能の人』のいくつかのカットを思い浮べたりもしたが、水門だけ狙って方々を探索する、このまるで現実的な有効性を持たない、つまり何の得にもならなければ、誉めてくれる人もそんなに多くはないだろう、徒労をモノともしない精神には、脱帽すると同時に「こうで、なくちゃね」という共感の思いを深くした。ぜひ高尾事務所のHPを参照して頂きたい。 |
| http://www.bunny.co.jp/ |
| |
| # 今週末には鳥取を訪問するので、早い時期に追加、更新を行なう予定。また、今月中には掲載できるであろう「文献目録」のことを考えると、わたしの頬は自ずとゆるむのである。調査、研究の成果を提供して頂く立場としては、責任重大であるが、このHPを開設した、最初の存在理由となるに違いない。 |
| (2000・7・3 上映委員会/山崎邦紀) |
| |

|
|
『第七官界彷徨 尾崎翠を探して』上映委員会 |