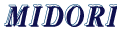
資料コーナー

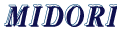 |
資料コーナー |
 |
●尾崎翠「地下室アントンの一夜」論● |
第三章 「(地下室にて)」の世界 |
|
|
|
| 17は「地下室にて」の冒頭部分であるが、このように「地下室にて」は、語り手「私たち」によって設定されている場所である。この「私たち」は、「いつも静か」な「空の世界」に「太陽、月、その軌道など」が点在しているように、「一人の詩人」の「限りなく広い」「心」に点在している、「私」の総体ではないかと考える。(注7) この地下室は、「人々のすでに解つて居られるとほり、此処は一人の詩人の心によつて築かれた部屋である。」と紹介される。この「詩人」を論者は土田九作と解釈する。作品中に「詩人」と指示されるのは土田九作しかいないからであり、「地下室アントン」を想定したのも「僕」=「土田九作」だからである。 「地下室にて」においては、「松木氏」「幸田当八氏」「土田九作」の三人が登場するが、前二者が「氏」という敬称で呼ばれるのに対して、土田九作には敬称が無く、「土田九作」という裸のままの呼びかたである。これは、語り手「私たち」が、「地下室アントン」を想定した九作の身に沿っているからではないだろうか。 また、みずからを「僕」とあらわす「土田九作」が「地下室にて」には登場する。ここで、詩稿へ放たれていた「僕」を我が身に回収し、統合した「土田九作」本体を確認することができる。 また、この地下室においてそれぞれの登場人物には、それぞれにひろがりが付されている。松木と当八には「動物学の前途には涯しない未墾地がつづいています。」、「心理病とは殖える一方のものです。僕のノオトは足りないくらゐでした。」とあるように、それぞれの研究分野であり、心におもいえがくものについて、また九作については、「土田九作は、踏幅のひろい階段をゆつくりと踏んで降りた。」とあるようにその身体の存在する場所について。 |
 |
|
|
|
| 17に「氏は行く先き先きの人間に戯曲を朗読させては帰つて来たのである。多分人間の音声や発音の中には、氏等一派の心理学に示唆を与へるものが潜んでゐるのであらう。」とあるように、幸田当八は「人間の音声や発音」を採集していた者である。幸田当八は、「松木日記」において松木が「聴心器」を用いて過剰に音を聴いていたよりも、より一層過剰な音を聴いてきて、その音をその身体に溜めている。標準量をはるかに越えた「音」が含有された当八の身体から、外部へ向けて「音」の意図のない滲漏が起こっていると考えると、この部屋は他の空間よりも「音」の密度が高まっているはずであろう。このような「音」の密度が高い場所だからこそ、正常な聴覚が失われ苦しんでいる土田九作にとっては、治療の場所として適切で有益であるのではなかろうか。 18に「地下室の扉がキユ-ンと開いて、それは非常に軽く、爽やかに響く音であつた。これは土田九作の心もまた爽やかなしるしであつた。何故ならば此処はもう地下室アントンの領分である。」とあるように、「うんと爽やかな音の扉」を欲した土田九作の願いはかなえられ、彼の聴覚は「地下室アントンの領分」において正常なものへと回復し、さらに「今晩は。僕は、途中、風に吹かれて来ました。あなたですか、小野町子が失恋をしてゐるのは」とその場に響く音をみずから発し、幸田当八との会話が成り立っている。 また扉は「キユ-ンと」開いて、その音は「非常に軽く、爽やかに響く音」であるが、地下室の扉は地上と地下の境界であり、地下室の扉が開く瞬間は、「天上、地上、地下」が空間として垂直に一瞬繋がる瞬間であり、当八、九作、松木の三人がそろう瞬間でもある。ここにおいて土田九作の心は爽やかになるのだが、地下室の扉の「爽やかに響く音」は土田九作の心に響いて「爽やか」にしたのみでなく、同時に「天上、地上、地下」という空間にも響きわたり、この「一夜」を「爽やか」にしたのではないだろうか。 また幸田当八による「三人のうち、どの二人も組になつてゐないトライアングル」という言及があるが、作者の尾崎翠が意図したかどうかは不明だが、トライアングルとは三角形の楽器を指す言葉でもある。 さてこの瞬間とは、何らかの力がはたらかない限りは、ふだんは決して繋がることのない「天上」と「地下」とが繋がる瞬間である。「天上、地上、地下」と、当八、九作、松木の対応関係はそれぞれどのようになるのだろうか。地下室に最初から居て「土田九作」=「僕」が「地下」を発想するきっかけとなった「遍歴ノオト」の作者とされる当八を「地下」に対応させよう。当八と九作のあいだの二番目に地下室に着いた松木を、「天上」と「地上」のあいだにある「地上」に対応させることとする。そして「地下」と最後に繋がったのは「天上」であるので、「地下室」に最後に降りてきた九作を「天上」に対応させてみる。そうすると、「地下」と「天上」が滅多に出逢うことがないのと同様に、当八と九作とは、滅多なことでは出逢うことがないのではないか。それなのに二人が出逢わなければならなかったのは何故だろうか。第三節において考察したい。 |
 |
|
|
| 第二節末尾で提起した問題について、考察したい。まず18の後半の会話の部分の検討から始める。 |
|
|
「松木氏は…恋愛会話に加はらなかつた。」とあるように、松木はこの会話に加わっていないので、最後の「さうとは限らないね。此処は地下室アントン。その爽やかな一夜なんだ」は幸田当八の言っている台詞であると確定してよいだろう。 「地下室」には誰より先に着いていて、作品の冒頭部にその論述「遍歴ノオト」の引用が配され、作品の末尾にはその台詞が置かれる「幸田当八」とは、何者なのだろうか。 当八の「小野町子が失恋をしてゐるのは僕です」という台詞は、もともと所持していた当八への「恋」を失った「小野町子」が、当八への「恋」を回収できたわけでもなく、失ったということそれ自体を失くすことが出来たわけでもないということにもなり、したがって、小野町子から当八への「恋」が失われているということは、持続されているという意味をなす。この台詞はそのことの当八からの九作への認定という意味になる。「土田九作」=「僕」は、「九作詩稿」内で「あの夜の誰かに失恋をして溜息ばかり吐いてゐた小野町子は、もう失恋から治つたであらうか。それとも…………/しかし僕はもうよほど疲れたから、その続きを考へることを止さう。考へ続けてゐると、だんだん、女の子が失恋から治つてゐない気がして来て、おれは悲しくもなるんだ」と、小野町子が失恋から「治」ったかどうかに関して悲観的であり、その「謎」をとくまでに至っていなかったが、ここにおいて当八からその回答が提出されたこととなる。 「小野町子」を九作が持っている自己イメ-ジのひとつとして、「小野町子」イコール「土田九作」とし、両者の喪失感覚から対応関係を考えてみると、「小野町子」が「幸田当八への恋」を「失っている」状態とは、「土田九作」が「正常な聴覚」を「失っている状態」という対応になる。ならば、「幸田当八への恋」と「正常な聴覚」とは同じものを指すことになる。 「幸田当八」は「地下室アントン」において「心理医者」と名指される「治療者」である。「幸田当八」が「心理医者」=「治療者」であることは「地下室アントン」において初めて判明する。「九作詩稿」の「地上」部において、「小野町子」が失恋をしている相手の属性は不明だったが、「地下室アントン」においてはそれは治療者という属性を付される。これを付したのは、「地下室アントン」を想定、創造した「土田九作」、また彼を含む「私たち」にほかならない。 このように考えると、「治療者への恋」と「正常な聴覚」とが対応することとなる。ということは「小野町子=土田九作」は「治療者への恋=正常な聴覚」を喪失していることとなる。 ところで「僕」=「土田九作」は、「小野町子」に「片恋」をしているが、「それつきり」「逢ふこともなかつた」。また、「九作詩稿」の「地上」部では、「僕」は小野町子に恋をすることについて、「心情を囚へ」ると述べている。この状態を整理すると次のようになる。 |
| 〈「正常な聴覚」 を喪失している〉土田九作 が 〈「幸田当八という治療者への恋」を喪失している〉小野町子 に 再び「逢ふこと」 を喪失していて、心情を囚えられている状態。 |
 |
|
さて、「地下室アントン」にて土田九作の「正常な聴覚」と「幸田当八」そのものは、九作に回復される。残っている「喪失」は、「小野町子が〈幸田当八への恋〉を喪失している」こと、九作が町子に「逢ふ」こと、である。ただし、九作は「いま、僕は、殆ど女の子のことを忘れてゐるくらいです。」と述べていて、九作が町子に「逢ふ」ことの喪失については、「地下室アントン」においては「殆ど」「忘れてゐるくらい」にまで麻痺されて、感じなくてもよい状態になっている。いまひとつの「喪失」は、町子の「幸田当八への恋」についてであるが、九作は「町子」に「逢ふ」ことについて「殆ど」「忘れてゐるくらい」と述べているので、その「町子」が「当八への恋」を喪失していることをも、九作は「殆ど」「忘れてゐるくらい」であるとみなし得る。「地下室アントン」では、「地下室アントン」においてさえ回復されない「喪失」を、「外の風に吹かれ」てやって来たことにより、ここにおいては、感じなくてもよい状態となっている。 この「地下室アントン」には小野町子はあらわれなかったが、仮に小野町子があらわれていたならば、九作は小野町子に「逢ふ」ことになっていた。もし逢えたならば、九作にとって苦痛である、心情を「囚」えられていることはなくなり、心情を「とらわれない」状態になったかもしれない。そして、小野町子は幸田当八に逢い、彼女の幸田当八への失恋は、得恋になったかもしれない。それがありえたなら、「恋」を得、こころを「とらわれない」まったくの本来の自由さに、土田九作は回復しただろう。しかしそうはならなかった。小野町子はあらわれなかったのである。 幸田当八は、「再び詩人になれると思はないか」と九作に問いかけておきながら、九作が「さつきから思つてゐる。」とそれを肯定すると、今度は「そうとは限らないね」とそれを否定もしないが、肯定もしない。「再び詩人になれる」ということには聴覚の回復がともなうと考えられる。しかし「そうとは限らない」のならば、この「地下室アントン」の「一夜」とは、詩人土田九作にとって、「一人の詩人の心によつて築かれた部屋」という内的空間において、この一夜という時間においてのみ聴覚の回復が行われるという、あくまで小野町子のあらわれる本質的な治療ではなく、小野町子があらわれることのない、対症的治療、応急手当がほどこされる所であり時である。土田九作が感じた「爽やかさ」とはそのような性質のものである。 「小野町子が失恋をしてゐるのは僕です」「さうとは限らないね」と決定的な判断を下す「幸田当八」とは、土田九作の内的世界では「治療者」の姿をとってあらわれる、「聴覚」などの感覚を含む、生命の根底をつかさどっている何者かではないだろうか。土田九作にとって「幸田当八」の判断は、心身が安定した状態で営まれているかどうかの自己判断の根拠となり、その「遍歴ノオト」のようなものは、従うべき指示なのではないか。だからこそ、滅多に出逢うことのない二人は、松木という媒介者をもって、出逢わなければならなかったのではないだろうか。この出逢いの目的は、土田九作自身が喪失されない=死なない、廃人にならない、発狂しない、ようにすることだろう。 作品の最後の、「さうとは限らないね。此処は地下室アントン。その爽やかな一夜なんだ」という台詞は、幸田当八として形象されている根底的な判断を下す何者かからの「おまえは治っていない」というメッセ-ジの提示であり、また同時に「わたし自身は治っていない」という土田九作自身の自覚でもあるのだろう。 異常をきたしている正常ではない感覚(ここでは聴覚)がある場合、その回復が可能ならばそれを目指すのが、個の生存率を高めるためには妥当であり、必要なものであろう。しかし、状況が悪化するにせよ、好転するにせよ、この作品には、以後の可能性だけが残されている。土田九作の聴覚が以後、正常な状態への回復へと向かうのか、聴覚の完全喪失へと向かうのかは作品からは判断できない。けれども、聴覚の異常に苦しむ土田九作にとって、たとえ対症的治療であっても休息となりえたこの「地下室アントンの一夜」は、貴重なものであっただろう。 |
 |
|
|
|
| 土田九作が欲したのは「何処かの国の黄昏期」という至極曖昧な時、所に住んでいた、「アントン・チエホフという医者」の「微笑」の「表情」に「似て」いる「うんと爽やかな音の扉」を持つ、「すばらしい地下室」である。 ただ、しかし「アントン・チエホフ」は「むかし」の人であるので、いまここにはいない。九作はこの「表情」そのものを決して得ることはできない。得られたとしても、そのものでなく「似て」いるものなのである。しかし、「似て」いるものを得るには、ただ九作本人がある対象を、ただ「似て」いるとさえ、おもうことができればよいだけである。「聴覚」などもともと身に沿って存在していたものとは異なり、「アントン・チエホフ」は初めから九作の心のなかにしか存在しないものである。それゆえ、他の何者がその存在を否定しようと、九作自身がその存在を否定しなければ、「アントン・チエホフ」の「微笑」は彼の心のなかに永遠に存在し続けることができる。 「地下室アントン」は九作にとって対症的治療の場であると論じてきたが、この治療がなければ、彼は最悪の場合、生命を失っていたかもしれない。最終的に九作には、みずから想定した「地下室」の扉を「アントン・チエホフ」の「微笑」に「似て」いるとおもうことができるだけの力が残っていた。だから「(地下室にて)」の語り手「私たち」は、九作が地下室に到着し、「扉が開い」たときのことを、「非常に軽く、爽やかに響く音」「ここはもう地下室アントンの領分である」と述べたのであろう。この述懐は「アントン・チエホフ」の「微笑」というかたちを、九作が心のなかにおもいうかべることができたことの証である。これをおもいうかべること無しには、「非常に軽く、爽やかに響く音」もあり得なかっただろう。 心のなかにおもいうかべるかたち=イメ-ジを成立させることは、感覚に異常をきたしている者にとっては困難なことであろう。しかも九作にとってそのイメ-ジとは、救いをもとめて成り立たせたものであった。第三節末尾で述べたように、作品からは、以後九作の聴覚の異常が悪化するのか好転するのか判断できない。以後の可能性だけが残されている。このあと、状況が好転するのならば、このイメ-ジは九作にとって生へ向かう端緒と成りうるであろう。しかし悪化するのであればそれは死へ向かうということでもあり、ならばこのイメ-ジは、生きているという状態にあった九作がみることのできた、最後のイメ-ジとなるのかもしれない。どちらにせよ「動物学者を殴りに行く」という、自ら創出した仮象という自己を破壊する、自殺行為よりも、「微笑」の表情を心のなかにおもいうかべることができたということは、詩人にとってやはり「遥かに幸福」だっただろう。そして、それは詩人が「天上、地上、地下」を幸福なものとしてイメ-ジを成り立たせることができたという、詩人の心のあかしである。 |
 |
|
『第七官界彷徨 尾崎翠を探して』上映委員会 |