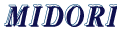
資料コーナー

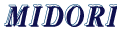 |
資料コーナー |
 |
●尾崎翠「地下室アントンの一夜」論● |
第二章 「(動物学者松木氏用、当用日記より)」の機能 |
|
|
| 「松木日記」は一人称「余」によって語られている。松木は「九作詩稿」においては、「僕」が創りだした仮象としての人物であるが、この「松木日記」はその仮象としての人物が語っているものだと解釈する。それゆえ、普通の日記ではあり得ない、日記でありながらの空間の移動が行われるのだと考える。この点については第二節で考察を試みたい。まず第一節では「松木日記」の前半部分について、「九作詩稿」と対照しつつ、「抒情詩人」と「松木夫人」の機能について考察したい。 |
|
| さて、松木に付された属性は「動物学者」であるが、「九作詩稿」に無かったもので、「松木日記」にはあらわれるものとして挙げられるのは、「草は青くパンは白い。豚の鼻は色あせたロオズ色。」とあるような鮮やかな色彩表現である。また松木は「聴心器で豚の心臓状態を聴く。」とあるように、「聴心器」によって、普通に生活していては聞こえない音までも聴いている。「九作詩稿」の「僕」よりも、視覚と聴覚の過剰さが「松木日記」の「余」の表現にあらわれている。 また、樹木に繋がれた豚が「非常に懶い態度で苦悩」する様子や、繋がれたまま歩いて行った豚が「向ふの丘に一方ならぬ郷愁を感じ、且つ繋がれた後脚は非常に自由を欲してゐる」様子、自由にならないことを理解した豚が「樹木を中心に渦状を描きつゝ後退をはじめる。地上に休む。」という様子は、第一章第二節で検討したような、「僕」の思考態度の比喩として描かれているのではないだろうか。 そのように考えてみると、この「松木日記」には、視聴覚表現の過剰さと喩的表現という一般的に「詩」に現れやすいとみなされるものが、「詩稿」と名指される「九作詩稿」よりもゆたかに表れている。また「九作詩稿」内において「僕」は松木の論文の標題「季節はづれ、木犀の花さく一夜、一罎のおたまじやくしは、一個の心臓にいかなる変化を与へたか」について、「この標題を読んだとき、僕は、動物学者松木氏を、一人の抒情詩人と間ちがひさうであつた。」と述べている。この標題は、「僕」が松木を心理透視者ではないかとおそれ、ひれふすことになり、「僕」を苛むきっかけになったものでもある。さらに松木に対しては、「僕は、恋をしてゐるとき恋の詩を書けないで、恋をしてゐないときに、かへつてすばらしい恋の詩を書けるんです。僕を一人の抒情詩人にしようと思はれたら、僕の住ゐに女の子の使者なんかよこさないで下さい。」と述べている。「僕」はこの詩稿内においては、松木が女の子の使者をよこした故に「抒情詩人」になれなかった者であり、「僕」によって語られるこの詩稿は「抒情詩人」の書いているもの、イコ-ル「抒情詩」、ではないことが明らかである。またこのような「僕」の主張から、「僕」は「恋の詩」を「抒情詩」のひとつと考え、「恋をしてゐないとき」という条件があれば、自分もそれを書くことが可能であると考えていた(もしくは書いていた)と解釈できる。一方で「僕」は、松木を「抒情詩人」とほとんど近しい者とも考えている。視聴覚表現の過剰さと喩的表現は抒情詩に特有のものというわけではないが、抒情詩にとりわけあらわれるものでもある。 これらから、「僕」に属していた「抒情詩人」という属性は、松木へ移動していると考えることができる。 またここで「松木夫人」について考えてみたい。「松木夫人」は「九作詩稿」の「僕」から「夫人と僕とは、地上の約束において姉弟である」と語られる、「僕」の「姉」である。また「松木日記」において「余」はもちろん彼女を「妻」と語る。この女性は松木との結婚前は「僕」の姉であり、「僕」の側に属性があったのだが、「僕」が自分に敵対しているとみなす松木の妻となり、いまや松木ともども「つねに僕を曲解してゐて、正しい理解をしようとはしない」状態にある。 このように「抒情詩人」と「松木夫人」とは、「九作詩稿」において、もとは「僕」に属していたものが、「僕」から離れて松木へと属性が移動して、「僕」を苛むものとなったという点において、同様の機能を担っていることがわかる。 |
 |
|
|
|
| 「松木日記」は「日記」であるにも関わらず、日記の語り手「余」は日記内で「余は思い切つて出掛けてみることにしよう。/漸く土田九作の住ゐに着いた。」というように、空間を移動する。この日記を書いているのが、仮象ではない、九作とは別個の人物である「余」ならば、このような逸脱はあり得ないだろう。この点からも、動物学者松木という人物は「九作詩稿」内の「僕」によって語られ、創出された仮象であると考える。仮象であるならば、必ずしも現実世界の掟どおりでなくても、それ以外の行動をとることが出来る。仮象である「余」のことを、その作者である「僕」は、思いどおりに左右することが出来るからである。 |
 |
|
|
|
| 「松木日記」における語り手「余」は、「土田九作の住ゐ」に着いて、「九作詩稿」を読む。「余」によって語られる「詩の帳面」の内容は、「九作詩稿」とほぼ内容を同じくする。(注6)そして、詩稿の作者である「土田九作」と、「九作詩稿」における語り手「僕」とを「余」は同一人と見なす。ここにおいて、「余」によって、詩稿の作者と語り手として分離していた「土田九作」と「僕」とが統合されたのだと解釈できる。「松木日記」の最も大きな機能はこの統合であり、このために「松木日記」の部分も設けられたのではないだろうか。 また、土田九作の部屋の灯について「余」は、「どうも、非常に暗くて不健康な灯だ。余まで何となく神経病に憑かれてしまひさうだ。」と述べる。これは灯であって、「土田九作」本体ではないが、彼の部屋の灯であり、「余」ではなく「土田九作」に属するものである。松木という仮象の人物は、この「灯」について「病」と認識していることから、自分を創り出した「僕」について、病んでいるという認識をしている。「九作詩稿」においては、「僕」自身が「医者」をもとめるという態度はあったが、自身を「病」として認識するという態度はみられなかった。「松木日記」において、「僕」によって創出された仮象である松木は、「土田九作」と「僕」とを統合し、また彼を病者であると認定した。その役割を終えて、松木もまた「地下室アントン」へ向かうところで「松木日記」は終わる。 |
 |
|
『第七官界彷徨 尾崎翠を探して』上映委員会 |